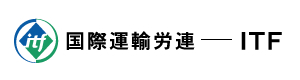| 2005年4〜6月 第19号 |
| ■誰に対してオープンなのか? |
 |
| |
オープンスカイ政策
誰に対してオープンなのか?
国際航空業界を50年以上支配してきた市場アクセスの規制が「野放しの」オープンスカイ政策に移行しつつある。航空労組は国が一定の影響力を保つべきだと主張する。
1944年、52カ国が米国のシカゴに集まり、その後の国際航空輸送の基礎となる協定に合意した。こうして、航空輸送サービスは「二国間による航空サービス協定」をもとに決定されるという原則が出来上がった。輸送量、路線、使用する空港、輸送価格などは二国間の交渉により決定される。
シカゴ条約により確立した二国間協定体制は、50年以上、国際航空法の不可欠な部分をなしてきた。A国が自国の3空港へのB国航空機乗り入れを許可する代わりに、A国の航空機もB国の3空港へ着陸できるといった具合だ。安全と保安の問題はこの協定の基幹部分であり、通常互恵的なもので、国際民間航空機関(ICAO)により監視される。
しかし、1970年代以降、航空輸送にも米国と欧州が推進する自由化が浸透し始めた。より自由な協定が考案されるようになり、政府による輸送量や価格面での規制が排除されていった。これがいわゆる「オープンスカイ」協定であり、今後さらに政府の就航路線や使用空港に関する規制も緩和されていく可能性がある。
オープンスカイ協定は、基本的に二国間、または地域内の各国において、航空サービス市場へのアクセスを規制緩和するというものだ。そうしてA国またはA地域とB国またはB地域が相互に航空輸送の規制を取り払うことを許可される。どの航空会社がどの空港を使い、どの路線を使うかは市場が設定する需要により決定する。2002年までには世界の約70カ国で約85のオープンスカイ協定が実施されるようになった。そのうちの3分の2は米国が関係している。2004年には、10地域でオープンスカイ協定が実施されるに至った。 |
|
 |
市場の占有
航空輸送産業の規制緩和を支持する者たちは、規制緩和により過当競争は改善されると主張する。しかし、実際は、規制緩和により少数の国際航空大手がますます力をつけ、中小航空会社は価格競争に敗れ、市場から退場を余儀なくされている。規模の経済から利益を得られるほど多くの航空機を所有する大手企業は、以前より低い価格でより多くの路線を利用できるようになり、使用できる空港の数も増えた。オープンスカイでは、中小企業は大手に太刀打ちできず、市場シェアを失い、倒産を余儀なくされる。その結果、一部の国でナショナル・フラッグ・キャリアが消滅し、一握りの大手航空会社が市場を占有するようになった。
乗客にとっては、オープンスカイはしばしば選択肢の減少と航空券料金の値上がりをもたらしてきた。
|
|
 |
安定と安全
2001年以降、航空輸送産業は不安定な市況に悩まされてきた。それまでは規制により航空業界の安定性が保たれていた。規制があるため、消費者は通常どおりのサービスを常に受けることができ、企業は長期にわたって路線を標準化することができた。しかし、規制緩和された市場では、好況時は輸送能力を上げることができるが、不況になると危機的な状況に陥る。路線が頻繁に開設されたり、閉鎖されたりし、航空券料金の乱高下も激しく、消費者の信用もすぐに崩壊する。
二国間協定には拘束力のある安全・保安基準が含まれていたが、規制緩和により、危険にも安全や保安の議論から経済的な議論が切り離されていく。利益を追求する中で、まず初めに切り捨てられるのが安全・保安対策になるだろう。そうなれば、航空会社の従業員、乗客、一般市民を大きなリスクにさらすことなる。 |
|
 |
航空労働者に及ぼす影響
航空機の運航コストのおよそ25〜30パーセントが人件費であるといわれている。不況時には労働者が真っ先に影響を受ける。消費者に提供する価格を一定に保つため、変動するコストを吸収しようと、航空会社は労働者の賃金、労働条件、手当などを攻撃の対象にし始める。その結果、従業員は非正規雇用に転換されたり、柔軟な働き方を求められるなど、雇用契約が不安定になっていく。
通常、オープンスカイ協定では労働条件の問題は経済的な問題とは無関係と考えられる。労働基準の安定に関する問題は、国際民間航空機関(ICAO)や国際労働機関(ILO)のような国際機関が今後も監視していけばいいのだが、そうした国際機関での議論が経済的問題と関連性をもたなければ、航空会社に労働基準に関する取り決めを遵守させるインセンティブが欠けてしまう。 |
|
 |
労働組合の方針決定
航空輸送はサービスの供給という商業的役割を超えた、より広範な役割を担っている。貨物や旅客の輸送サービス、あるいはそうしたサービスが存在しないことは、実に深遠な経済的意味をもっている。例えば、航空会社がある地域への輸送サービスから収益をあげられないと感じる時、その地域は世界の他の地域から切り離されてしまう可能性がある。また、民間航空と国家主権は非常に重要な関係にある。誰が自国の領空をどのように使うことができるのかを決定する権利を国が保持することが重要だ。そして、航空輸送産業の優先事項を選定するのは、自由市場ではなく、国家であるべきだ。
世界貿易機関(WTO)のサービスと貿易に関する一般協定(GATS)が航空輸送市場まで踏み込んでそのルールを決定していいのかという点については、各国政府の間でもコンセンサスが得られていない。ITFはそのような選択肢には断固として異議を唱えている。特に、経済的な規制と安全・保安面の規制の間にこれまで存在してきた関連性が断ち切られることをITFは懸念している。
飛行権を完全に自由にすることは、乗員や乗客の安全を脅かし、安定性を危険にさらし、途上国の中小企業が大手により市場から駆逐されることにつながり得る。このような、あらゆる要因が航空労働者の雇用、労働条件、安全を脅かす。したがって、ITFの加盟組合は、航空輸送産業の発展とそれを管理する協定は、協定に参加する国どうしの互恵の原則に根ざしたものであるべきだと考えている。また、航空協定は、労働者を含むあらゆる利害関係者の保護を念頭に置いて締結されるべきだ。
|
|
 |
| オープンスカイに関するITFファクトシートはから取り寄せることができる。 |
 |
| 自国の航空輸送産業を発展させるためにITFが勧めること: |
| ■ |
商業的な理由から安全と保安を妥協してはならないことを国が保障する。保安と安全に関する責任と説明責任の所在を関係者間で明確にする。 |
| ■ |
国は、持続可能で計測でき、かつあらゆる利害関係者の意見に開かれ、あらゆる活動の責任の所在を確立し、訓練・安全・保安などの主要分野に的を絞った「賢い」経済規制を設けるべきだ。 |
| ■ |
今後の航空産業の発展は、公正さ、互恵主義、安全・労働・社会基準、雇用と労働条件の保護、質の高いサービス、公共サービスとしての気風などに根ざしたものでなければならない。 |
| ■ |
労働組合とその代表者は、航空産業の将来に関わる、あらゆる政府間の話し合い、二国間交渉、その他の航空輸送関係協定の議論に参加すべきだ。 |
|
|
 |
| |