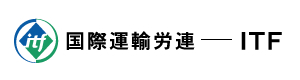| No.19/2005 |
| ■ITFインスペクター |
 |
| |
港で活躍するインスペクター
ITFインスペクターのネットワークは、世界の主要な港で拡大を続けている。異なる3大陸で新たにインスペクターに任命された3名に話を聞いた。 |
|
 |
カロライナ、プエルトリコ
エンジェル・フェリペ・ガルシア・コルチジョがプエルトリコ担当のITF常勤インスペクターに任命されたのは、2003年11月。
インスペクターとしての経験は比較的浅いものの、1977年以来、国際港湾労働者協会(ILA)のメンバーとして活動を続けてスペイン語と英語にも堪能である。
フェリペの話では、カリブ海の港、サン=フアン港に入港する船舶と貨物が増えているという。コンテナ船やカーキャリア約28のクルーズ船の母港にもなっており、世界最大のクルーズ船母港となっている。
将来はポンセ港を拡張して、増加する入港船に対応するこが期待されている。現時点での交通量の増加と、将来の港拡張に伴って予想される増加のため、新たにインスペクター制度を導入してITFによる支援を本格化するメリットは大きいということで意見が一致した。
|
|
 |
台中、台湾
サンダース・チャンは台中港のITFインスペクターに任命され、2004年7月に着任した。中華海員総工会(NCSU)のメンバーであり、代表、監査役また常任役員にも選出された経歴の持ち主である。
1984年国立台湾海洋大学(NTOU)を卒業、1992年には、英国、ウェールズのカーディフ大学で海洋法を学んだ。
サンダースはこれまで、船舶業界の両面を見てきた。チ・ユアン・ナビゲーション号では3等および2等航海士として乗船し、アメリカン・プレジデント・ラインでは営業部長、またユーミン・マリン・トランスポーテーション社では課長を勤めた経験がある。
台中港は、台湾の急速な経済成長に対応するために建設された港であるが、現在は50もの外洋船用埠頭を備え、取り扱う貨物も幅広い。オートメーション化もかなり進んでおり、2003年の年間取扱量は、計約8,100万トンに上った。2021年末までには、埠頭を64まで増設し、取扱量を約1億2000万トンに拡大する計画になっている。
2001年には船員クラブが設立され、医療サービスやITF出版物の配布、船員の未払い賃金の計算などのサポートを行っている。台中港での経済活動は急速に拡大し、その重要性も増している。台湾で活動するインスペクターは他にもいるが、特に台中港でITFの活動を早急に強化する必要がある。
|
|
 |
モンバサ、ケニア
ジャマ・カミスがモンバサ担当のITFインスペクターに任命されたのは、2003年6月。ケニアの港湾労働者組合のメンバーでもある。
ジャマは警部、税関職員を数年間勤め、ケニア港湾局でも講師など、様々な任務についた経験をインスペクターとしての現職に生かしている。ケニヤ港湾労組では書記長を13年間務め、ITF港湾部会のアフリカ地域議長にも選出された。ケニア労働組合中央組織の執行委員も経験した。
モンバサ港は、ケニアやその他ウガンダ、コンゴ、ルワンダなどの内陸国に通じる玄関口にあたり、同時にタンザニア、モザンビーク、インド洋上諸島への主要な通過港でもある。その港湾施設と戦略的な位置から、モンバサ港に寄港を希望する船舶が増えており、現在拡張・近代化工事が進行中である。結果としてFOC船の入港も増え、ジャマはFOC船にありがちな様々な問題の解決に奔走する毎日だ。港で取り扱う荷物は、輸入貨物や国連向けの食料援助物資だ。輸出品も農産物から、セメント、繊維、石鹸などの一次産品まで多彩である。
現在ITFが直面している大きな問題は、船員遺棄と未払い賃金である。ケニア人船員が外国船舶に雇われるようになり、外国船舶の虐待、低賃金、組合費の押収などの問題が顕在化した。
ジャマが特に懸念しているのは、モンバサ港に何ともひどい状態の船舶が入港してくることで、こういった船舶が一体どのようにして証明書を交付されたのか疑問に思っている。ある港を出港したもののモザンビーク海峡で転覆し、船員の生命と貨物を失った船舶もあった。「船主は、ケニアの深刻な失業問題につけこみ、当局に影響力をもっている。一方で、船員は貧困と孤立、脅迫に苦しんでいる」とジャマは語った。
|
|
 |
世界中で船員を援助(PDF)
ITFインスペクターの詳細な連絡先については www.itfglobal.org/seafarers/msg-contacts.cfm を参照のこと。 |
|
 |
インスペクターたちの多忙な一日
FOC船・基準以下船撲滅キャンペーンの最前線に立つ人々は、どんな毎日を送っているのだろうか。 |
|
 |
アニカ・バーニング
ストックホルム、スウェーデン
「訪船すべき船があるだろうか?」−インターネットで港の様子をチェックすることから、私の一日は始まる。この日は2、3の船が目についたので、ITFのデータベースで調べた。このデータベースには必要な情報が全て入っていて、訪船する船を決める際に非常に便利だ。
ITF承認協約の有無、船員リスト、同僚のインスペクターによる前回の訪船記録などをチェックし、あるアンティグア=バーブーダ籍船を訪ねてみることにした。ITFの記録によれば、ラトビアにいる同僚が数ヶ月前に協約を締結するよう求めたものの、協約締結に至らなかったとのこと。またドイツのインスペクターからは、船員の給与と残業手当に関して問題があるという報告もあった。
目的地はケパン港。車で170kmくらいのところなので、港にいる様々な人に連絡を取る時間は十分ある。特に、港湾組合の代表をしているマイクには必ず連絡を取る。ボイコットなど、港湾労働者のサポートが必要な場合に備え、マイクに事前に連絡を入れることは非常に重要だ。
その時間になると、ITFのロンドン本部も活動を開始しているので、電話で同船に関するもっと詳しい情報を問い合わせたところ、結局のところ、ITF協約を締結していることが分かった。
目的地に着くと、まずデッキで2人の部員から給料や労働時間、契約期間について話を聞く。それから船長に会いに行く。船長は風変わりなユーモアの持ち主で、最初、書類を見せることを渋った。私はこういう状況ではかなり説得力のある話し方ができる方なので、船長も最後には折れて書類を見せてくれた。不正の疑いは何らなかったが、一部、不足している書類があったので、ラトビアのインスペクターに電話して、書類が無いこと、その書類は船内に常備すべきだということを船会社に伝えてもらった。船会社は直ちに該当する書類を船に送ると約束した。
念のため、もう一度、船員と話をする。この船員たちが問題を隠していることはあり得ないだろうと確信し、礼を述べて下船する。マイクをつかまえて、この船は問題がないため、貨物の積み降ろしを継続するように伝える。
車でストックホルムに戻り、ITFのデータベースに報告を打ち込む。次回、この船を訪船するインスペクターが参考にできるように、報告は出来るだけ詳細に行うことを常に心掛けている。
|
|
 |
シュー・チュン・アン
ヒューストン、アメリカ
2003年2月からインスペクターとしてITFとテキサスの国際船員組合で仕事を始め、2年になる。今でも初めて訪船した時のことは忘れない。ロシア人の船員に34,846米ドルの給料と帰国のための航空券を獲得し、解決したケースだった。その時の乗組員だった、ウラジミール・V・ドジェンコ船長は、今でも私に恩義を感じ、連絡をくれている。
インスペクターになる前は、便宜置籍船のAB船員として5年間働いた。その間、基準以下の生活環境、低賃金、給料の不払い、食糧不足、不当な待遇、劣悪な医療サービスなど、あらゆる苦労を味わった。そのため、船員をサポートする今の仕事には真剣に取り組んでおり、喜びも感じている。
毎朝Eメールをチェックし、インターネットでヒューストン港の交通情報に目を通し、入港する船舶を確認する。ここで一日の大まかな訪船スケジュールを立てるが、船員から緊急で連絡が入った場合はそちらを優先させる。日課として行う訪船に関しては、まずITFのオンライン・データベースで過去の訪船記録を調べる。
最初の訪船地に向かう途中、港湾神父や船食業者など、港で働く人間と話し、これから訪船する船やその乗船員の評判や情報を収集する。
船員から苦情を受けた際は、まず個別に船員と話をし、彼らの言い分を聞くようにする。その後、問題の本質について船長と話し合い、団体協約もしくは雇用契約に従って問題解決を図るよう努力する。賃金が未払いである場合は、船主に連絡を取り、支払日に再度船に足を運んで、船員が確かに給料を受け取ったか確認する。
検査手順はすべてITFオンライン・データベースに打ち込む。不当な処遇を受けていた船員のサポートを出来ることを非常にうれしく思っている。多くの船員から届く礼状やクリスマスカードに、ITFのサービスや活動に対する感謝の言葉が綴られているのもうれしい。
|
|
 |
カシーム・アウグストス
ケープタウン、南アフリカ
オフィスに着くとまず新聞に目を通し、港の様子をチェックする。次に他の港に電話をしてさらに情報を集め、ITFのウェブサイトにアクセスして、自分に割り当てられた訪船すべき船舶すべき船舶があるか確認する。
訪船する船舶には優先順位をつける。第一に船員から依頼があった船、次にITF協約の締結の有無に関わらず、問題がある船、次に協約を締結していない船、最後が協約を締結している船、の順だ。
査察に入る前に、船名、国際海事機構(IMO)番号、旗国を調べ、その船舶に間違いないかを確認する。
タラップを上りデッキに出て、まず不正の兆候がないかを観察する。こうした観察からも労働環境や生活環境に関して実に多くのことが分かる。それから乗組員と話をし、どれくらい賃金を貰っているかを聞き出す。キッチンと貯蔵庫のチェックも船長に会う前に行う。
船長と面会し、必要事項を聞きだした後、ITFの出版物を渡し、HIVエイズに関する情報を船員に伝えるよう注意を促す。次の寄港地までの無事な船旅を祈りつつ船を後にする。
万事上手くいった。次の船も同じ手順で査察する。その日の訪船についての報告をITFのオンライン記録に打ち込み、一日の仕事が終わる。
|
|
 |
大堀二三男
横浜、日本
船員からは電話やEメールで、メッセージが多数届く。安全設備に不具合があるという報告から、情報提供の依頼まで内容は様々だ。ついこの間も、ロシア人の船長から名古屋港に停泊できるか港湾当局に聞いてくれという電話がかかってきた。私のことを現地のエージェントとでも思ったのだろう。
身体のことについて相談してきたインドネシア人船員もいた。3ヶ月前、太平洋で獲ったマグロの水揚げのため、船が清水港に入港した際、左腕を骨折したという話だ。
この船員に会いに船を訪ねた時、彼は働き続けられるかどうかを非常に心配していて、日本人の医者から渡されたレントゲンの写真を私に見せてくれた。重症だと思ったため、次の目的地の釜山で別の医者に見てもらうことを勧めた。船長にもその旨を話し、必ず病院に行かせるよう頼んだ。同時に、その船員が雇用契約どおりの賃金を受け取っていないことも明らかになったため、船主に未払い賃金を支払うよう求めた。
結局、彼は釜山で手術を受け、現地のITFインスペクターのサポートを受けながら1ヶ月滞在し、未払い賃金も受け取り、本国に送還された。
また、先日は川崎の配乗会社から、多様な国籍の船員が混乗する船で問題が起こったという電話を受けた。私は配乗会社の川崎事務所で、2人のインドネシア人船員に会った。彼らはもう船には戻らない決意を固めていた。エンジン室に安全上の問題があるという。ジャカルタの配乗会社本部は、既に交代要員を用意しており、この2名の帰国費用は出したくない、契約破棄の原因になったのは会社側の過失ではないと主張した。
そこで、ポート・ステート・コントロール検査官に電話でこの船を検査するよう依頼したところ、メインエンジンに安全上の欠陥があることが判明し、船は2週間港に拘留されることになった。2人のインドネシア人船員は本国に送還された。
最近受信したEメールに、賃金の未払いに関するものがあった。中国人船員からで、約9,000米ドルの賃金を受け取っていないという。船員と家族にとっては深刻な問題だ。
私は機会があれば、EQUASIS(国際船舶データベース)のホームページ(www.equasis.org)にアクセスして、船に関する情報収集をするように、と必ず船員に勧めている。EQUASISは、ITFも含めた多数の国際海事組織がサポートしている制度で、船員は登録さえすれば、船舶の所有者、管理者、建造年、型式、積載トン数、ポート・ステート・コントロール記録、ITF協約締結の有無など、あらゆる情報を調べることができる。
|
|
 |
| |