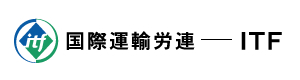| 2004年10〜12月 第17号 |
| ■航空会社の所有権と経営権 |
 |
| |
航空各社は航空不況を乗り切り、市場シェアや利益を拡大させるために、合併、買収やアライアンスという手段を行使してきた。しかし、航空業界には企業側のこのような動きを扱う法的枠組みや規制制度はまだ存在していない。こういった状況の中で航空会社の合併・再編が加速すれば、航空輸送の公的側面の軽視、労働条件の悪化、そして、お決まりの雇用削減につながる危険がある。
所有権はどのように変わってきたか?
航空輸送は昔からグローバルな性格を帯びているが、航空会社と国との間には伝統的に緊密な関係が存在する。つまり、航空会社は国営であるか、株式の過半数が当該国の居住者に所有されている。国は外国航空会社に与える運航許可を保留にしたり、取り消したり、条件を付けたりする権利を保持することで、自国の領空や空港へのアクセスをコントロールしてきた。
これはつまり、航空会社が国際運送権を付与されるためには、しかるべき「国籍」を必要とすることを意味する。政府はこのシステムを使って、自国の航空会社が外国で与えられる運送権と自らが外国航空会社に与える運送権との相互主義的バランスを保ってきた。
一方、国際航空運送事業者はここ10年間、自由化、グローバル化の流れの中で、コスト圧力の増加に対応するために、外国航空会社の買収、外国での子会社設立、地域的・国際的アライアンスへの加盟や、合弁事業の立ち上げなどによって、外国での資本基盤の増強に力を入れてきた。このようにして、所有権の多国籍化が進む一方、航空各社がグローバル企業としての活躍を可能とする規制の見直しを求める中で、航空業界や労働組合にさまざまな課題がつきつけられている。 |
|
 |
なぜこの問題は労働者にとって重要なのか?
関連する多くの問題が労働者に大きな影響を及ぼすからだ。特に重要な問題は・・・ |
| ■ |
民営化:既に国営航空会社の多くが完全民営化されているが、国と航空会社の緊密な関係は依然として存在する。例えば、近年の航空不況でも各国政府は介入し、ナショナルキャリヤーに経済支援を行った。もし、この緊密な関係がなくなれば、政府の直接支援は減り、航空会社の生き残りはさらに難しくなり、労働者の雇用も脅かされるだろう。 |
| ■ |
規制緩和:民間航空の経営管理は安全・保安や労働規制と密接に関係している。規制緩和で航空会社の合併や大手航空会社による買い占めが可能となり、労働者や乗客の安全・保安を守ってきた規制が経営から切り離される可能性がある。 |
| ■ |
弱肉強食:不公正競争防止のメカニズムを確保することなしに、国際的な合併を認めれば、資金力のある大手のみが市場を支配することになる。規模のメリットを武器に略奪的な価格設定をし、自らの事業拡大のために豊富な資金を費やしていく大手航空会社に国内の中小航空会社が対抗することはできない。また、外国航空会社の成功は資本や人的技術の国外流出という国内の犠牲の上に成り立つ。 |
| ■ |
公共の利益の喪失:国と航空会社の緊密な関係は、当該国家の社会・経済的利益を守るために維持されてきた。航空産業は国家経済の発展や社会目的の達成のために不可欠であり、単なる営利事業とは性格が異なる。しかし、国と航空会社の関係が断たれれば、この「公共の利益」という不可欠な要素が「利益追求」の影に埋もれてしまうだろう。 |
|
|
 |
空のFOC導入か?
海運産業でほぼ全面的な規制緩和が実施された結果、「受益船主」と旗国の関係に規制が及ばなくなった。そのため、労働力が最も安く、労働規制が最も甘く、秘密厳守を約束する国に船籍を置く「便宜置籍船制度(FOC)」が誕生した。
FOCの誕生以降、海の安全・保安レベルは最悪の状態に保たれたままだ。そればかりか、船主を誘致するために競って法規制を緩和しようとする国も現れ始めた。
ITFが懸念しているのは、規制緩和で航空輸送が外国資本に開放されれば、法規制が甘く、コストのかからない国に自由に運航拠点を移すことができる、空のFOC制度が誕生することだ。これが現実となれば、海運と同じように、基準が切り下げられ、規制をめぐる混乱が生じるだろう。例えば、アルゼンチンの航空会社がアイスランドに登録された機材を使い、欧州の乗務員を乗せて運航した場合、問題が発生した時に法的管轄権を行使できるのはどこの国になるのだろうか?
このような混乱を避けるために、ITFは国際民間航空機関(ICAO)などの国際機関を通じて、明確かつ厳格な基準の設定を求めている。 |
|
 |
交通運輸労働者への影響は?
企業は景気変動の中で利益を維持していくために労働条件や賃金の切り下げを追求する。航空会社の合併でも最も大きな影響を被るのは労働者だ。ある米航空会社の合併に関する調査によると、合併は客室乗務員の収入に直接、相当な影響を及ぼすことが分かっている。
それでは、合併は具体的に労働者にどのような影響を及ぼすのか? |
| ■ |
通常の労使交渉手続きが妨げられる |
| ■ |
合併後のさらなる成長に資金が費やされるため、賃上げや労働条件向上のための資金がなくなる |
| ■ |
合併で市場シェアが拡大する結果、賃金・労働条件に対する企業側の決定権が強まる |
|
| 合併は通常、運航路線・便数の削減につながるが、これは利用者にとって不都合となるだけでなく、雇用削減という形で労働者にも悪影響をもたらす。 |
|
 |
安全・保安責任は?
国と航空会社の緊密な関係が存在している場合、安全・保安責任の所在は明確だ。国が定めた安全・保安規定に航空会社が従えばよいからだ。しかし、国際的な合併の場合、この極めて重要な問題に対する責任の所在があいまいになりがちだ。乗客と乗務員の両方にとって重大な安全・保安問題が国家間の管轄権の隙間に転落してしまう危険がある。 |
|
 |
新規制で危険を回避できるか?
ICAOは管理された、段階的自由化には概ね賛成の立場を示しているが、現在の体制では国境を越えた合併や航空会社の新たな経営形態にはうまく対応できないことも認識している。新たな規制体制を構築し、安全、保安、労働者の利益を最優先事項として扱うべき、というのがITFの考え方だ。
「国際的な枠組みがしっかりと出来上がるまでは、所有権(ownership)と経営権(control)の基準緩和はソーシャル・ダンピング、安全・保安ダンピング、管理監督レベルの低下を招くだけだ」−ICAO航空運送会議(2003年3月)に提出されたITFの論文より− |
|
 |
航空アライアンスとは何か?
グローバル化対策の一環として、航空各社はアライアンス(企業提携)を推進してきた。アライアンスとは、航空各社が購入、フライトスケジュール、グランドハンドリングなどの業務で協力し、情報を共有しながら相互の発展・成長を目指す、世界規模の航空連合を意味する。
アライアンスは合併の不完全かつ一時的な代替戦略といえよう。航空会社がアライアンスを選択する主な理由は、政府間交渉で運送権を付与されるにはグローバルなアイデンティティーではなく、その国の「ナショナル」キャリヤーとしてのアイデンティティーが必要とされるからだ。
アライアンスの例としては「ワンワールド」「スターアライアンス」「スカイチーム」などがある。航空各社は自社で手荷物取扱い要員やサービス要員を抱える代わりに、同じアライアンスのメンバー同士で資源を融通しあい、コスト削減、利益増大をめざしているのだ。 |
|
 |
航空労働者への影響は?
多数のマイナスの影響が考えられる。 |
| ■ |
航空各社の労働条件の調和(harmonization)は通常、最低の水準に合わせる形で行われる。 |
| ■ |
コードシェアリングで運航便数が減る |
| ■ |
業務・設備の共有で雇用が削減される |
| ■ |
乗務員やサービス・スタッフは異なる航空会社の仕事を求められるようになる。外注の増加で、使用者責任の限られた、不安定な短期雇用が増える。乗務員やサービス・スタッフは異なる航空会社の仕事を求められるようになる。外注の増加で、使用者責任の限られた、不安定な短期雇用が増える。 |
|
|
 |
ITFの対応は?
ITFは数年前から拡大するアライアンスへの対応策を講じてきた。その中でITFは、アライアンスを構成する航空会社の組合が以下のような分野で団結し、前進できるよう、調整役を務めてきた。 |
| ■ |
アライアンスを超えた連帯行動 |
| ■ |
情報共有 |
| ■ |
団体交渉とアライアンスレベルでの労使交渉 |
|
ITFは三大アライアンスに対抗する加盟組合のアライアンスとして、「ワンワールドアライアンス労組連合」「スターアライアンス労組連合」「スカイチームアライアンス労組同盟」を組織している。
ITF加盟組合はこれらのアライアンスの絶え間ない変化、企業間の新たな国際協力体制に対応するために、さまざまな連絡・協力戦略を開発中だ。 |
|
 |
| |