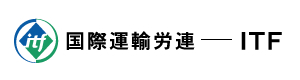|
 |
| 2004年10〜12月 第17号 |
| ■読者の声 |
 |
| |
保安と労働者の権利
機械工・航空宇宙労働者国際組合(IAM)は全航空労働者に対する適切な訓練、特に客室乗務員に対する保安訓練の実施を要求してきた。保安・訓練の監督責任は政府にあり、航空会社だけに押し付けてはならないと考えている。
保安は最優先事項だが、航空労働者のプライバシーの問題にもきちんと対処されなければならない。また、誤った個人情報に関する紛争処理手続きの確立も必要だ。これらの個人情報は人事異動や解雇の根拠に使われることがあるからだ。
アウトソーシングも旅行者や労働者の保安上の脅威となっている。早急に解決する必要がある。
最後に忘れてはならないのは、航空という非常に重要な産業で働く労働者は保安上の脅威ではなく、むしろ、最初のかつ、唯一の防衛線として機能する場合が多いということだ。常に敬意と尊厳をもって航空労働者を扱わなければならない。
オーウェン・ハーンスタッド
(米国、IAMAW)
デンマークではまだ法律が整備されていない。現在、組合は経歴検査で従業員に不利な結果が出た場合、公正な第三者の前で法的手段に訴える機会を確保し、判決の結果を公開する制度を要求している。この作業は進行中だが、組合は全ての国会審議に深く関与している。
クロース・リンデガード
(デンマーク、SiD)
オーストラリア連邦政府は当初、「船舶および港湾施設の国際保安(ISPS)コード」を使って、組合やわれわれが組織する港湾労働者や船員を抑圧しようとしたが、われわれがロビー活動や実力行使を行った結果、ISPSコードを適用させながらも、労働者の権利と労働条件を守ることに成功した。
ハワード政権は誇らしげに国家の保安政策を発表しているが、そこには2つの致命的な欠陥がある。輸入空コンテナの非検査と便宜置籍船(FOC)優遇策だ。FOCは海上保安に対する最大の脅威であるにもかかわらず、自国籍船に課せられている責任のほとんどを逃れている。FOCの真の受益所有者を寄港前に開示させる法律ができるには、まだ時間がかかりそうだ。
パディー・クラムリン
(オーストラリア、MUA)
組合員は検問や検査が増えたり、身分確認や監視が強化されたりすることは仕方がないと思っている。しかし、既に法的に港への入場を許可された従業員に無差別検査を実施するのは反対だ。勤務表に名前が載っている、制服を着た社員がゲートでの検査を済ませ、写真付の身分証明書を携帯して、社用車で現れたとしても港湾施設に自由に入れないというのは過剰反応としか言いようがない。
オークランド、リトルトン、オタゴの組合員は個人検査と検査中の「拘束」を拒否している。オタゴ港の企業は「保安レベル1」の段階では従業員や従業員の車に対する検査は行わないと約束した。
ポール・コーリス
(ニュージーランド、RMTU)
「保安レベル1」の段階では無差別検査は認めないというのがわれわれの方針だが、政府は港湾当局からの圧力を受けて、われわれに無差別検査を強要しようとしている。
インスペクターの訪船が拒否されるなど、ITFの査察活動にも障害が出ている。訪船が拒否された場合には、全ての港湾と電話で連絡をとり、その船の荷役を行わないようにしている。
トレバー・ハンソン
(ニュージーランド海運労組)
ISPSコードが発効し、訪船に24時間前までの事前通告が求められるようになったため、ITFの査察活動が大幅に制限されている。24時間前の通告は非現実的であるばかりか、ほとんど不可能だ。
ITFの査察活動がISPSコードに妨げられることがないように、現在、われわれは、ITFコーディネーターと一部のボランティア・インスペクターを対象に最高レベルの保安検査を実施するよう、要請している。
キャシー・ウェラン
(ニュージーランドのITFコーディネーター)
ISPSコードのある条項は、港湾当局の保安措置によって労働者の権利が侵害されてはならないと規定している。しかし、われわれが組織するアンティグア港湾当局保安部では全く逆のことが起きている。経営側は保安部職員の雇用を継続したがらず、代わりに、港湾業務に精通していない民間の警備会社を使おうとしている。
アリック・ダニエル
(アンティグア労組)
米国に寄港する船員は全員、ビザを持っていなければならない。会社からもビザを取得するように言われるが、実際に米国領事館に行くと、発給を断られることもある。訓練生からこれまでに米国に寄港したことのあるベテラン船員まで、このような問題に直面している。ビザの発給の拒否は船員のキャリアに汚点を残すことになる。インド船員組合(NUSI)は現在、米議会に陳情書を提出するためのデータを収集中だ。
アブドラガニ・Y・セラン
(インド船員組合)
米当局の規制により、タンカーに乗り組むインドネシア人船員の仕事がなくなっている。その理由は2つ。1つはタンカーが危険物を輸送するため、テロの懸念があるからだ。もう1つは、公には言われていないものの、インドネシアがイスラム教国だからだと確信している。
ビザの申請手続きが大幅に変わり、船員は結果が出るまで何ヵ月も待たされるようになった。申請には、ビザ発給後に雇用を保証するという使用者側の書簡も必要になったが、ビザが発給されるかどうか分からない段階で使用者が雇用を保証するのは難しい。
ハナフィ・ルスタンディ
(インドネシア船員組合)
問題はターミナルにあると思う。あるターミナルは、ゲートを開放したまま守衛をつけるとコストがかかるため、ゲートを常に閉鎖し、従業員にはIDカードを持たせて入退場させているため、乗組員は上陸することができない。医者や歯医者に行くことさえできないと言われている。
フリッツ・ガンゾーン
(デンマーク航海士組合)
* 2004年7月1日に「船舶および港湾施設の国際保安(ISPS)コード」が発効、船社や港湾当局は保安検査の実施と保安計画の実行を求められている。 |
|
 |
HIV・エイズに対する組合員の考えは?
自宅から遠く離れ、さまざまなストレスにさらされる交通運輸労働者はHIVの感染リスクが高いと言われている。
多くの組合がHIV・エイズを職場の問題としてとらえようと努力している。HIV・エイズに関する教育、医療ケア、反差別措置などの条項を団体協約に盛り込ませた組合もある。
一方、文化的・社会的障害、特に女性に対する男性の姿勢、行いなどの問題と格闘している組合もある。
今月の質問は「HIV・エイズに対する組合員の考え方は変わったか?その具体例は?」
あなたの意見をケイ・パリス()まで。
締切日は10月29日。意見は編集される場合有。 |
|
 |
| |
|
 |
|