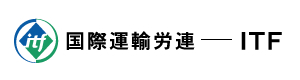|
 |
| 2004年10〜12月 第17号 |
| ■コメント |
 |
| |
ナーブルスからタクシー来ず
ヨルダン川西岸地区の交通運輸労組は、極めて困難な状況下、社会的に不可欠な役割を果たしているとセーラ・フィンケは言う。
7月にヨルダンで開催されたITF-ICFTU(国際自由労連)小地域ワークショップに参加した際、ナッセール・ヨウンは救急車に乗って現れた。
ヨウンの身に何かあったわけではない。ヨウンが1万6千人の路面運輸労働者を代表しているヨルダン川西岸地区からヨルダンヘ移動するわずかな距離の移動すら、緊急手術の必要があるという医師の診断書で、イスラエル当局に移動の必要性を納得させる必要があるからだ。
パレスチナの交運労働者とその代表者は、日々、これ程までに大きな困難に直面している。
2003年には、イスラエル軍がヨルダン川西岸地区でトラック35台を爆破し、多数の市民が生活を奪われた。計157ヵ所もあるイスラエルの検問所も交運労働者に深刻な影響を与えている。ほんの短距離の移動に数時間かかることもある。そのため、タクシーはナーブルスとラミューラーの間の運行を停止し、今では都心部でのみ運行している。
2000年のインティファーダ(反イスラエル闘争)以来、日常の商業生活が途絶えてしまったことで、交通運輸労働者やその他の産業の労働者は明らかに大きな打撃を受けている。
「企業が月給を下げるのは、もちろん不満だが、だからといって反対することもできない。従業員を一部解雇する決断が下されても、理解するように努めなければならない。本来の闘いの姿とは言えないけれども」とナッサールは言う。
あらゆる困難にも関わらず、ナッサ−ルの出身労組、運輸一般労組は「断固として組合活動と組合員へのサービスを継続する心構えだ」と彼は言う。組合が組合員に基本医療保険を提供したり、パレスチナ当局に抗議してきたことが(経験不足と政治情勢ゆえに限界はあるものの)、これまでどれ程パレスチナの交運労働者を救ってきたか、ナッサールはこう述べる。
「パレスチナ政府は、車を爆破された労働者からも税を徴収しようとしていた。また、車齢18年以上の車をタクシーにしてはならないという規則を採択したが、ヨルダン川西岸地区で、新しい車を手に入れることなど不可能だ。そこで、組合は政府の政策に抗議し、問題解決のために政府から一年の猶予を勝ち取った。」
ナッサールによると、組合員数がここ5〜6年で5倍に増えたが、それは全て組合活動を効果的に進めてきたからだという。
「積極的に活動し、現場の組合員ともよくコミュニケーションを取っている。昨年は、大会を開催することもできた。」
2000年、組合は、ヨルダン川西岸地区の現状に一定の規制をもたらすことを求めて、パレスチナ評議会(パレスチナ議会)に新しい労働法の草案を提出した。「かつては軍事規則が支配していたため、ある程度の規制が存在していたが、今では規制が影をひそめてしまった。評議会も努力はしているが、議員の多くが抑留されていることもあり、正常に機能できずにいる。」
ナッサール自身もこれまで22回逮捕されており、8年間イスラエル側に拘束されていた。
しかし、ナッサールの決意は固い。「組合としての機能を改善していきたい。他の組合の支援があれば可能だと思う。」帰り際、救急車を目の前にそう語った。 |
|
 |
|
ナッセール・ヨウンはヨルダン川西岸パレスチナ地区の運輸一般労組の委員長。セーラ・フィンケはITF情報政策部長および女性部長。 |
 |
米労組の連帯強化
米政権の反労組政策は11月の大統領選で変わるかもしれない。しかし、選挙の結果がどうであろうと、米国の交通運輸労組との国際協力強化の必要性は何ら変わることはない−デビッド・コックロフトITF書記長
世界交通運輸労組の連帯は、国内、地域内の協力を通じて、ITF加盟組合を国際活動で結集させることだ。
ITFでは、米州以外の地域活動は順調に発展しているが、米州に至っては、北米、中南米、カリブ海諸国間の経済・社会・文化的格差が大きいため、米州全体で連帯を構築するのが難しい。
米州地域最大の米国では、海運や航空労組は昔から国際活動が組織維持・拡大に直接関係あることを認識していたが、陸の組合にグローバル化の影響について説得するのは簡単ではなかった。
しかし、10年前に北米自由貿易協定(NAFTA)が誕生し、北米地域の自由化が進むにつれ、陸の組合の考え方も変わっていった。米州自由貿易地域(FTAA)が予定どおり2005年に発効すれば、さらにその傾向が強まるだろう。
そこで近年、ITFは米国の加盟組合と共に国際運動をより効果的に実施する方法を追求してきた。
今年の3月、私はアントニオ・フリッツITF米州地域部長と共にワシントン(ナショナルセンターの米労働総同盟産別会議本部)でITF加盟組合の代表者らと会合をもった。本来、ITF米州地域事務所(在リオデジャネイロ)は米州全域を管轄することになっているが、実際の業務のほとんどは中米やカリブ海諸国に集中している。米加盟組合との会合の目的は、ITFが米加盟組合のために何ができるか、米州地域で必要とされている活動は何かを話し合うことだった。
米国の運輸産業にもますます多くの多国籍企業が進出してきている。これらの多国籍企業の中には、本国では組合を認知し、交渉もしておきながら、米国では組合潰し用のコンサルタントを雇っているものもある。彼らは市場自由化を追い風に、組合が長年の闘争で勝ち取ってきた労働条件を叩き潰そうとしている。 |
|
 |
ネットワークの構築
加盟組合との会合で明らかになったのは、労組に逆風が吹く中で、米国向けのITF活動をもっと強化する必要があるということだ。これを受け、ITF書記局は現在、各部会と米州地域事務所との連絡体制の強化や、グローバル化に関するキャンペーンや教育活動の支援強化を進めている。
その第一段階として、2005年初頭に交通運輸とFTAAに関する特別会議をメキシコシティーで開催し、中米・カリブ海諸国の主要組合に加えて、米国、カナダの全加盟組合を招聘することになっている。また、UPS、DHL、TNT、Fedexなどの大手インテグレーター(小口の国際航空貨物輸送事業者)の労組間の国際協力を目指す世界会議も計画中だ。さらに、既に実施中の航空アライアンスをベースとした労組間の活動や、グローバル化をテーマとする加盟組合の教育活動支援にも力を入れていく。
米加盟組合とITFの連絡強化のための担当者も2人、ワシントンに配置する。1人は北米東岸港湾労働組合(ILA)法律事務所のインゴ・エスダーズ。東岸やメキシコ湾岸の港湾労組幹部にFOCキャンペーンについてもっと知ってもらうのがエスダーズの仕事だ。もう1人は米労働総同盟産別会議(AFL-CIO)海運部のダン・ダンカン。海運以外の組合にITFの活動への参加を促すのが彼の役目だ。2人ともITF本部書記局付のパートタイムでの勤務となる。2人の配置は暫定的なもので、今後、米加盟組合と相談しながら見直しを行う。将来的には、より本格的な「米州」機構の設立も考えられるが、これは、関係組合に具体的な利益をもたらすことが確実な場合に限っての話だ。
米労働運動は近年、厳しい環境にさらされている。それ故に、米労働界にとっての目下の最重要課題は11月の大統領選でブッシュ政権を追放することだ。しかし、誰が次期大統領に選ばれようと、米国の一般労働者にとって、国際問題がますます重要になっていくことは間違いない。特に交通運輸部門では今後何年間も「連帯のグローバル化」の意義が薄れることはないだろう。 |
|
 |
|
デビッド・コックロフトはITF書記長。 |
 |
| |
|
 |
|