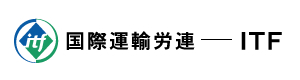| No.22/2008 |
| ■海事労働条約 |
 |
| |
ILO海事統合条約広範な批准を
革新的な海事統合条約が、その可能性を最大限に発揮し、全世界の船員の生活が改善されるよう、組合は懸命に活動を続けている、とケイ・パリスは報告する。
2006年2月、海運産業は、「船員の適切な雇用条件を確保するために必要な、あらゆる最低基準を包括するILO海事統合条約の採択」という歴史的一歩を歓迎した。これにより、明確な文言で書かれた船員の「権利章典」が遂に完成し、54以上の国際水準が近代化され、一方で、新条約実施のための証明書発行と証明書の検査システムも導入された。また、条約の技術面の修正を簡潔に行う手続きも明記されている。すなわち、条約の修正が容易になったため、現状への適応も容易になった。
しかし、他のILO条約と同様、海事統合条約(MLC)も、直ちに実施されることにはならない。一定の加盟国による批准という発効要件、即ち、この場合は世界の船腹量の少なくとも33%を占める、最低30カ国による批准という条件が満たされるのを待たなければならない。
この記事を執筆中の現在、世界船腹量の10%に相当する便宜置籍国のリベリアだけが同条約を批准している。一方、批准に向けて、より綿密に準備を進めている国も多い。
欧州議会の議員は2007年3月に、EU加盟国の批准目標を2008年とする計画を推進することについて投票したが、批准がいつになるかは定かではない。
各国政府、使用者、ITF率いる労働組合を代表するILOのソーシャル・パートナーは、できるだけ速やかな批准に向け、活動を継続している。ILOのクレオパトラ・ドンビア・ヘンリーILO国際労働基準局長が言うところの「質の高い海運業界にとって不可欠な要素」を新たに創出しようとする機会は、まだ失われていない。ソーシャル・パートナーは、「ハイレベル」ミッションを、主要海運国やMLCに関心の高い国が主催する地域セミナーに派遣し、各国政府や産業界のトップたちと議論を進めることに専心してきた。
発効要件を満たす批准が確保されれば、海事統合条約を批准していない旗国の船舶であっても、優遇されることはなくなる。あらゆる国の船舶が、批准の有無に関わらず、検査を受け、基準を満たしていないと判断されれば、拘留の対象となり得る。
各国の批准のプロセスと平行し、ITFとその欧州組織である欧州運輸労連(ETF)は、MLCの主要条項のうち、現行のEU規則に包含されていないものをEU規則に取り入れるため、欧州船主協会(ECSA)と交渉を展開している。この交渉で合意された全ての条項がEU指令に盛り込まれることになり、MLCを批准していない欧州の港においても拘束力を持つことになる。 |
|
 |
変化の見通し
上述の通り、条約を実際に実施するため、海運関係者が目に見える努力を続けていることから、海運産業のあらゆる利害関係者は、海事統合条約が海運産業を改善する極めて大きな可能性を秘めていると感じていることは明らかだ。
ファン・ソマビアILO事務局長は、「労働の世界における画期的な進展」として海事統合条約を歓迎している。ECSAのディエルク・リンデマンは、「この条約は、労働条件についての国際条約に存在する穴を埋めるものになるだろう。労働条件に対する配慮は不可欠だ」と、述べた。
国際海事機関(IMO)のエフシミオス・E・ミトロポウロス事務局長は、MLCの採択により、IMOの安全、訓練と職務基準、環境の3大条約*に続き、労働基準が海運規制の第4の柱へ高められた、と評価する。
証明書システムの下に、船主は、旗国が承認する「海事労働証書」と「海事労働適合宣言書」を携帯しなければならない。後者は、条約を実施する上で関係する国内法が、航海を通して適切に実施されるよう、船主が計画を立て、提示することが求められている。つまり、船長は、継続的に条約が遵守されていることを証明するために、絶えず記録しなければならない。また、問題が生じた際は、船内、陸上を問わず、速やかな解決を促す手続きも用意されている。
英国のNAUTILUS船員組合(以前の英国船舶職員組合(NUMAST))の書記長で、ITF船員部会の議長を務めるブライアン・オレルは、海事労働条約を「船員のための権利章典」として、真っ先に歓迎した。
「自分たちの権利を理解し、その権利を享受するためには、どうすればよいのかを、船員自身に理解してもらいたい。また、権利が受けられない場合、船員は、その状況を正す権利を有していることを理解してもらいたい。ここで言う権利とは、定期的に賃金を受け取る権利、必要な場合は本国に送還される権利、適切な休暇を取る権利、通信手段にアクセスする権利、苦情を申し立てる権利などのことだ」と、オレルは言う。 |
|
 |
欧州の情勢
EU指令の適切な文言をめぐり、ECSAと最近交渉を行った後、オレルは次のように報告した。「交渉では、労使双方が、中央協定に海事統合条約の主な要素を盛り込む方向で努力することに力を注いだ。この中央協定は、後にEU指令の文言の基礎を成すことになる」
EU指令(前頁の囲み記事を参照)により、海事統合条約は、欧州において、特に、EU加盟国がこの条約を批准しなかった場合には、特別の「強制力」を持つことになる。しかし、労働組合は、EU指令が発効する前に、海事統合条約が発効要件を満たせるよう、先ずILO加盟国に条約を批准させようと懸命に活動している。
「EU指令が発効すれば、EU加盟国はこれに従わざるを得ないのだから、それで十分であり、MLCの批准は必要ないと考える国があるかもしれない。しかし、EU諸国出身の船員の多くが、EU指令の適用を受けない外国船で働いている」と、オレルは述べる。
EU指令の文言について合意することにより、欧州における海事統合条約の主要な項目の取り込みと実施が、さらに裏付けられることになる、とオレルは言う。「何よりも、ソーシャル・パートナーは、これらの条項をEU指令に盛り込む意欲があることを、EU加盟国に明確に伝えることができる」 |
|
 |
批准に向けての前進
一方で、あらゆる利害関係者が、条約を批准する必要性について、高い意識を持ち続けなければならない。既存のILO海運関係条約を批准し、実施するに当たり、各国政府が抱えてきた問題を克服しようとする動きが、海事労働条約を推進する原動力の一つとなった。海事統合条約は、船員の権利を明記する一方で、ILO加盟国が国内法の枠組みの中で、働き甲斐のある人間らしい労働条件を実施する方法に一定の柔軟性を持たせることにより、既存の諸条約に伴う問題を解決しようとしている。
もちろん、加盟国が法制面で乗り越えなければならない問題は依然として多い。例えば、全ての船舶が出航前に、船員の賃金、居住設備、休憩設備などの項目において、最低基準を満たしていることを証明する証明書を国から取得しなければならないが、旗国は証明書を発給する権限をどの機関に与えるべきなのか?また、寄港国はどの機関に証明書の検査を実施する権限を与えるべきなのだろうか?
海事統合条約の批准に乗り出した国は、解決しなければならない法制上の問題に多数、直面している。政労使のソーシャル・パートナーは、特に船腹量を多く保有する国の批准を奨励し、支援することを決めた。そのため、ITFの海事関係組合の代表も、フィリピン、パナマ、ロシアなどの主要国へのミッション(調査団)や、日本、アルゼンチン、ブルガリアで行われた各地域のセミナーに参加してきた。
各国へのミッションの派遣は、現在も行われている。各国政府は、必要な法制面の変更を実施する準備があることを示しており、ミッションは、これまでのところ、概ね成功している。 |
|
 |
推進力を維持して
2007年2月に行われた最初のミッションの一つが、パナマ・ミッションである。パナマには7千隻の船舶登録があり、最大の旗国の一つとなっている。ミッションを受け入れた後、パナマ政府は、海事統合条約を速やかに批准できるよう、法制面、行政面、運航面での変更を伴う行動計画を実施すると約束した。一方、ILOは規範を設定し、「協議および訓練のためのメカニズムを構築する」上で必要な技術的支援を提供する、とパナマ政府に約束したが、パナマ政府が条約批准に前向きだったことは明らかである。
パナマ・ミッションに参加したITF米州間地域事務所のアントニオ・フリッツ部長は、「パナマ政府がやる気を出したのは、世界最大の船舶登録国であるという国益だけではない。平等な労働条件を生み出すことで、船員の雇用機会が大幅に拡大する可能性がある、とパナマ船員組合が見ていることも一因だ」と、述べる。
「海運産業は、不当競争を防ぐため、世界共通の基準に合意する必要がある。労働コストは、通常、コスト削減の主な対象であり、しばしば、安全は二の次と考えられがちだが、パナマ当局も船員を搾取する従来のシステムが、確実に変化していることを理解したようだ。パナマ船員組合は、パナマ籍船に乗組むパナマ人船員の数を増やすための機会として、MLCを捉えている。これまでのパナマ政府の政策とは異なる視点だ」と、フリッツは語る。
海事統合条約が、労働供給国の経済にどのような影響を及ぼすのかについて、世界最大の労働供給国、フィリピンで懸念が広がっている。条約の主目的は、悪徳船主や悪徳用船主を根絶し、船員を保護することであるから、労働供給国への影響は、それほど大きくはないかもしれない。ILOのフィリピン・ミッションに参加したブライアン・オレルは、最低労働基準の実施が、比類なき最大の船員供給国にとって何を意味するのかについて、明確に説明してくれた。
「条約が批准されないうちは、フィリピン人船員の需要は依然として高いだろうが、条約が発効すれば、船主はMLCに適合した方法で、船員を募集せざるを得なくなるだろう。海事労働証書を発行する旗国が責任を負うことになり、船主は船員の募集が適切に行われていることを確認せざるを得なくなる。MLCを既に批准し、MLCに適合した船員募集メカニズムが既に確立している別の国に行く方が単純に楽だと考える船主が増えるかもしれない。そうなった時、世界最大の船員供給国としてのフィリピンの地位が、揺らぎ始める可能性がある」と、オレルは述べる。
しかし、フィリピン政府は、全ての運輸関係当局をILOミッションとの会談に参加させ、MLC批准を促進する決意の固さを明確に示した。ミッションの訪問により、フィリピン政府は、MLCで求められる新基準を自らの船舶が満たせそうもないと懸念するフィリピン船主のロビーイングに対して、より強い立場で対応することができた。
「実際、MLCが関係するのは外航海運だけで、一部、群島間の運航にも適用される場合はあるものの、木造船を含む内航船の多くは適用外となる。これで、条約批准の大きな障壁はなくなる」と、オレルは述べる。 |
|
 |
ロシアへのミッション派遣
ILOのロシア・ミッションも、ロシア連邦運輸大臣、国際協力広報局長、連邦大統領府顧問など、ロシア政府の高官と会談し、ロシア政府の条約批准に向けた明確な政治的意思を感じることができた。しかし、条約の実施に当たっては克服すべき問題が多く、問題克服には5年ほどかかることが予測される。
連邦運輸大臣が行動計画を策定しているが、先ず、ロシアが批准している既存のILO条約を実施する仕組みを創る必要があるなど、多数の問題が浮き彫りになった。例えば、「募集および職業紹介」に関するILO第179号条約の場合、この条約を監督する省庁が存在しない。つまり、同条約を遵守するかどうかは任意であり、マンニング会社が適切に管理されていない。MLCの募集に関する条項に適合するためには、この問題を乗り越えなければならない。また、ロシア連邦は、重要な旗国および寄港国であるとともに、労働供給国でもあることを考慮する必要がある。
旗国および寄港国による検査システムに課せられた多数の訓練要件も、難しい問題であることが判明した。それにもかかわらず、ロシアの船主はMLCの支援を表明しており、ロシア議会の下院も支持を約束した。ロシア議会下院の労働社会政策委員会委員は、ILOミッションとの会談の後、MLCの早期批准と実施を求める勧告を採択した。この勧告は、大統領に提出される予定である。
ロシア・ミッションに参加したITFのジョン・ウィットロー船員部長は、「非常に有益かつ生産的なミッションだった。このミッションにより、いくつものドアが開かれ、ロシアの条約批准に必要な措置が促進されることになろう。船員の身分証明書に関するILO第185号条約を実施するためにロシア連邦政府が講じると約束した手法は、非常に優れたものだ」と、述べた。
他のグローバル産業の労働組合も、海事統合条約の行方、すなわち、この条約により、世界貿易の9割を担う120万の船員を保護するための極めて公平かつ効果的な規則体系が、いかに発展していくかを見守っている。ソーシャル・パートナーが抱いた希望が実現するなら、経済問題の中心に労働者の権利を据えた壮大なグローバル・システムを各国のレベルで実施するという基本原則から、労働組合が学べる点は多いだろう。
*IMOの3大条約とは、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW)、船舶からの汚染防止のための国際条約(MARPOL)である。 |
|
 |
| ケイ・パリスは、2007年12月までの、ITF機関誌「トランスポート・インターナショナル」の編集者。 |
 |
新条約の主な条項
| ● |
船内の働き甲斐がある人間らしい労働・生活条件を保障する雇用契約には、船員と船主または船主代理人の双方が署名しなければならない。 |
| ● |
全ての船員は、雇用契約および適用される労働協約に従い、賃金の全額を支払われる。 |
| ● |
最長労働時間は、「いかなる24時間についても14時間」、「いかなる7日間についても72時間」とする。 |
| ● |
船員の疾病、傷害、船舶の難破、支払い不能、売船などの場合における船員の送還コストは、船主が負う。 |
| ● |
適切な大きさの居室および適切な暖房、換気、衛生設備、照明、病室を提供するなど、居住設備と娯楽設備については、特定の要件を満たすこと。 |
| ● |
船内および港において、船員が迅速に医療サービスを受けられることを担保しなければならない。 |
| ● |
効果的実施と遵守を確保するための施策には、労働基準遵守の証明制度も含まれる。海事労働証書と海事労働適合宣言書は、旗国が発給し、寄港国検査のために船内に備え置かれなければならない。 |
|
|
 |
| |