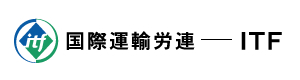| No.22/2008 |
| ■福祉 |
 |
| |
船員の命綱
港湾をベースとする福祉サービスは、船員の在港時間の短縮や航海期間の拡大などによる要求の変化に対応できなくなっている、とITF船員トラストの報告書は伝えている。
海運産業界の競争の激化は、入出港間隔の短縮、乗組員の少数化、一時上陸の短縮となって現れているが、さらに、船員が必要としている福祉施設へのアクセスの制限などが船員を圧迫している。
この不快な状況は、ITFのためにカーディフ大学国際船員調査センターが行った、一年間に及ぶ調査によって明らかにされた。「港湾をベースとする船員福祉サービス」(この報告書は、 からダウンロードすることができる)は、船員福祉サービスへの要望に関する調査の4,000人の回答をまとめたものである。
この調査によれば、多くの船員は海上で過ごす時間が長くなったため、港湾にある従来型の船員福祉施設を利用できる時間は減少していることが明白となった。
同時に、使用者側も、このような変化に見合った船員福祉サービスの開発を怠ってきた。 |
|
 |
福祉業務と業務形態
大多数(72%)の船員が、現在の契約による乗船期間中、船員福祉スタッフの訪船はなかった、と答えた。また、外部からの訪船者に会った船員も、ほとんどいなかった。彼らの福祉サービスに対する要求や期待は、現行業務の枠を超えるものであった。82%の船員は、舷門の近くまで来ることのできる移動式船員センター(小規模な店舗と電子メールなどのサービス)のアイデアに、積極的な反応を示した。
回答者の所属は100社以上に及び、各社の方針の相違により、船員福祉に対する要求も多岐にわたるものであった。一般的に船社は、船員福祉について非常に狭い視野しか持っていないため、彼らの提供する福祉は限られた娯楽設備が中心となっていた。けれども、この種の福祉の提供体制にも、大きな相違がみられた。ある船社の場合には、一隻当たり、毎月150ドルを福祉基金として、DVDやスポーツ用品に当てていたが、他の船社では、時間外手当または他の手当の中から、強制的に船内福祉基金を徴収していた。
この調査で得られた各社の方針、船主や会社の代表者との面談などの分析は、「福祉サービスの提供コストと利益の微妙なバランス」を示唆していた。 |
|
 |
港湾の福祉施設
多くの船員は港湾の船員センターの活動を高く評価していたが、港湾地域を徒歩で移動することの危険性、保安警備の強化などの点から、船員センターまでの無料輸送を要望していた。船員たちが名前を挙げた最も良い船員センターは、英国、西ヨーロッパおよび北アメリカの港湾のキリスト教系船員センターであった。最悪とされたのは、黒海地方やインド亜大陸のセンターであった。一般商店やカラオケ・バーなどのある商業センターの利用が多く、特に無料の交通手段が提供される場合に、船員の利用が増加している。 |
|
 |
接触を保つ
部員の大多数は、海上でのEメールの利用を、今でも認められていない。家族や友人との重要な唯一の接触手段を失っているのである。船内でEメールの利用が可能であると回答した船員は、16%に過ぎなかった。部員の場合には、僅か3%であった。さらに、Eメールの利用が許されている場合でも、回数やメッセージの長さが制限されたり、プライバシーがない場合や受信あるいは送信に料金の支払いが必要なケースも見られた。手紙は最も経済的な選択肢ではあるが、彼らは手紙を書くための十分な時間がないため、Eメールのほうが魅力的であると回答している。船主との面談で明らかになったことは、彼らが、船内のEメールを通じて故郷の家族と船員がいつでも接触できるよりも、船員が故国のニュースを知らない方が好ましい、と考えていることである。ある船社の代表は、「彼らは、故国にいる家族の出来事について、悩んでしまうのです」と、語った。 |
|
 |
一時上陸
一時上陸は、船員の肉体および精神を健康に保つために、極めて重要である。しかしながら、一時上陸は、海運産業の状況変化の影響を最も強く受けている。報告書によれば、64%は、かなりの期間、一時上陸がない、と回答した。また、一時上陸したと回答した船員のうち、36%は、平均して僅か2時間しか上陸できなかった、と答えている。
一時上陸ができない主な理由は、入出港の間隔が短いこと、船員のための交通手段が得られないこと、港についての情報が得られないこと、ISPSコード(国際船舶港湾保安コード)による上陸制限があること、などである。船社の代表らも、船員の一時上陸が制限される理由にISPSコードを挙げているが、彼らは異口同音に、一時上陸が船員の福祉にとっては重要である、と答えている。 |
|
 |
船員の要望
多くの船員が福祉の改善に必要な事項として挙げたのは、陸上の福祉施設(通信、ショッピング、信仰のための施設など)に行くための交通手段、船員福祉スタッフの訪船、寄港地の情報、船員福祉の必要性とISPSコードの実施のバランス、船内Eメールの利用などであった。
デビッド・コックロフトITF書記長は、ITF船員トラストの事務局長をも兼務しているが、「船員トラストは、大規模な建設プロジェクトへの支援から、頻繁な訪船に伴う小規模な移動業務への支援へと軸足を移した」と、語っている。
その他、船員トラストは、できる限り多くの船員が利用できる福祉プロジェクトにするため、船内通信設備の設置と、ISAN(国際船員支援ネットワーク)による無料電話サービスの奨励を目標に掲げている。
報告書の全文(英語のみ)は,
で閲覧できる。 |
|
 |
| ● |
港に船員センターがあることは重要だ。電話をかけられるのが何よりもうれしい。他の船の乗組員と会うこともできる。 |
| ● |
私が利用している唯一の連絡手段は衛星電話だが、非常に高い。船内にEメールはあるが、チーフオフィサーでさえ、仕事目的でしか使えない。私用で使うことはできない。 |
| ● |
上陸は非常に重要だ。ストレスを発散できる唯一の手段だ。船内では奴隷のようだ。他の人と触れ合い、違う顔を見ることが必要だ。 |
| ● |
コンテナ1個につき、1ドルのラッシング料をもらう。ラッシング料の10%が毎月、本船の福利基金に当てられている。 |
| ● |
一般的に、船員には、カウンセリングが必要だ。全ての船員が必要としているわけではないが、フィリピン人船員には特に必要だ。カウンセリングは、われわれの精神生活の一部だ。 |
| ● |
孤独感を解消するためには、訪船が必要だ。「元気?」「ここでの生活はどう?」「何か問題はない?」と、声をかけてもらいたい。 |
| ● |
公衆電話のない港は多い。ISPSコードの導入前は、携帯電話の行商人がやってきて、1分1ドルで電話をかけさせてくれた。しかし最近、彼らを見かけることはない。われわれにとって、家族と連絡を取ることは非常に難しい。特に、2〜3時間滞在するだけの港から連絡を取るのは難しい。 |
| ● |
われわれの海上生活をより良くできるものは非常に少ない。家族の声を聞くと、お金では買うことのできない幸福感を味わえる。 |
|
|
 |
| |