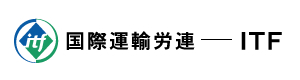| No.22/2008 |
| ■文化の交差 |
 |
| |
文化の交差
もし、貴方が海事産業で働けば、異なる文化を背景にした船員に、恐らく頻繁に出会うことになるだろう。ここに掲載したのは、主要な海運国(中国、英語圏諸国、フィリピン、アイスランドおよびロシア)の船乗りの伝統の香りを読者に味わっていただくために選んだ、幾つかの事例、物語、言葉やその他の文化的断片である。リポーターは、ヤスミン・プラブダス。
中国
中国には、7千年以上の船乗りの長い伝統がある。その最盛期は明朝時代(1368〜1644)であった。今日では、中国に50万人以上の船員がいる。
中国の船乗りの英雄「鄭和」の伝説
鄭和は明朝時代の人。彼は、27,000人の船員が乗り組む300隻の船団を率いて、1405年から1433年の間、アジアからアフリカにかけて、30カ国以上へ航海したと言われている。彼の通ったルートは西太平洋とインド洋を結ぶ航路で、西はペルシャ湾からマダガスカルに及んだ、と考えられている。鄭和の航海は、コロンブスのアメリカ大陸発見に先立つこと、87年前と記録されている。
いくつかの中国船員の言い伝え
●1尺の帆を上げれば、10尺の風が受けられる
●大きな船は、大きな借金の上を航海する
●古い木を使って、新しい船を造るべからず
●浜辺の決意は、世界の海につながる
●小さい船に、重い貨物は積めない |
|
 |
フィリピン
フィリピンは世界最大の船員国で、現在、約25万人の現役船員が、あらゆるタイプの船舶に乗り組んでいる。船員は、フィリピンの海外労働者の15%に過ぎないが、海外労働者の中で最大のドルの稼ぎ手である。
余暇活動
フィリピン人船員は、一般的に:
●フットボールよりも、バスケットボールを好む
●スヌーカーよりも、ビリヤードを好む
フィリピンの神話
遠い昔、大地、空、海は3人の神が治めていた。空の支配者だった太陽神には、ルナ(月)という名の美しい娘がいた。ある日、彼女が道を歩いていると、その道は彼女を国の外へと導いた。彼女は歩き続けて、空と海が接しているところに着いた。
彼女がまわりの美しい風景に見とれていると、突然、声が聞こえた。その声は、「おまえは、どこから来たのか?一番美しい人よ」と、たずねた。彼女があたりを見回すと、一人の若い男が微笑んでいた。彼女は、「私の名はルナ。太陽神の娘です」と、答えた。「私の名はマール。私は海神の息子です。わが王国にようこそ!」と、彼は答えた。まもなく、2人は親友になった。彼らは、大変、面白い話を、お互いに伝え合った。そしてルナの帰る時間がきたとき、彼らは、出来るだけ多く会おう、と約束した。彼らは、何度も会い続けた。そして、とうとう恋に落ちた。
ある日のこと、彼との密会を楽しんだ後で、ルナは喜びでいっぱいになって空の国に帰った。彼女は、あまりにも幸せだったので、彼女の秘密を一人の従姉に話してしまった。従姉は、ルナの幸せと美しさに嫉妬して、その秘密を太陽神に告げた。太陽神は、神の掟に娘が背いたことに腹を立てて、彼女を庭に閉じ込め、海神に使いを送り、彼の息子のマールが神の掟に背いたことを伝えた。海神は、息子のマールを海辺の洞窟に閉じ込めた。
ルナは、マールと再会したい、と願った。ある日のこと、彼女は苦労して庭から抜け出した。彼女は、彼との密会の場所へと急いだ。洞窟の中のマールからは、彼女の姿が水に写っているのが見えた。彼が洞窟から出ようとしたため、海が荒れた。ルナは長い間、待ち続けたが、マールはとうとう来なかった。彼女は、深い悲しみとともに家に帰った。彼女は、その後も何度か彼との密会の場所に行ったが、マールが現れることはなかった。
漁師たちは、今でも、ルナ(月)が昇るたびに海が荒れる、と信じている。「海が荒れるのは、マールが洞窟から脱出しようとしているからだ」と、彼らは言う。
よく使われるフィリピンの言葉
アパット=船長
へぺ=チーフ
ヘペ・クビエルタ=チーフメート(1等航海士)
ヘペ・マキニスタ=チーフエンジニア(機関長)
マエストロ・アモ=ボースン(甲板長)
マキナ=エンジン
クビエルタ=デッキ
パボール=港
エストレボール=左舷
タリ=ロープ
バルデヨ=甲板/船倉の洗浄
カルガダ=貨物
カイン=食べる
プエルト=港/バース
カイビガン=友人
カバヤン/カババヤン=同胞
クムスタ=今日は/ハロー
マアロン=大波/悪天候
ワラング・サホド=無給
ワラング・ペラ=金がない
ヨシ=シガレット
アラク=蒸留酒/ワイン/アルコール |
|
 |
アイスランド
アイスランドの基礎を建設した海の英雄への敬意を捧げるための「船員の日」ほど、アイスランド人に強い影響を与えている伝統はない。
アイスランドの「船員の日」の歴史は、首都レイキャビックおよび隣接するハフナルフョドルの船員組合が協力して、「船員の日」評議会を設立した1937年に遡る。その目的は、「1年のうちの1日をアイスランドの船員のために捧げて記念する」ことであった。第1回目の「船員の日」は1938年に挙行されたが、それ以降は毎年6月の第1日曜日と定められている。「船員の日」は、今ではアイスランド社会の一部となっており、1987年には憲法に定められ、11日しかないアイスランドの祝日の1つとなっている。
アイスランド国民は、この日、建国の基盤となった産業に敬意を捧げる。アイスランドの海辺の町や村では、祝賀行事が行われる。行事の中では、船乗りの仕事が披露される他、海上で命を失った船員や退職した船員、ならびに海運産業の開拓者に対する賞賛や敬意が示される。この他、ボート競漕、船舶展示会、ダンス大会、コンサートなどの明るい雰囲気の行事も行われる。この日は、全ての漁船が操業を休んで港内に係留され、乗組員は家族、友人や一般市民とともに祝日を楽しむ。
「船員の日」評議会の役割は、1939年に拡大された。評議会は、船員を可能な、あらゆる方法で支援したい、と希望した。船員の負担は過大であり、平均寿命が比較的短いことを遺憾に思った。「船乗りの負担を軽減するために、評議会はレイキャビックで老人ホームの建設と運営に着手し、1957年には船員老人ホームを開設した」と、「船員の日」評議会のG・ハルヴァルドソン議長は述べている。「1977年には、ハフナルフョドルにも新たに船員老人ホームが開かれた。これらのDASホームは、アイスランドの老人保護事業の先駆者だ。現在、700人が、これらのホームで生活している」 |
|
 |
ロシア
ロシアの船員の伝統は、17世紀末のピョートル大帝の時代に始まる。今日、ロシア船員の数は、12万人を超えている。
ロシアの特別な祝日
6月16日、ロシアの人々は、ネプチューン(海神)の日を祝う。伝統によれば、初めて赤道を越えた船乗りは、秘儀の洗礼を受けることになっている。新参の船員は、海水に浸たされるか、水泳プールに放り込まれる。その後、哀れな船乗りは、機械油がたっぷり塗られた船倉を、這って通り抜けなければならない。この儀礼を通過した船員は、ネプチューンの印章と儀礼の修了証を授与される。彼が次に赤道を通過する場合は、この儀礼修了証を示すことによって、儀礼は免除される。
商船船員と内陸水運労働者は、7月の第1日曜日が祝日となっている。
船員のために乾杯
ロシアでは一般的に、宴会などにおいて船乗りのための乾杯が行われる。この乾杯は通常、宴会の主要な乾杯の後に行われる。
ロシアのことわざ
ウォッカ抜きのビールは、風に向かって金を捨てるようなものだ。
よく使われるロシアの言葉
プリヴェット= ハロー
ロシーア= ロシア
カク・デラ?= お元気ですか?
ドルーグ= 友人
ダズヴィダーニャ= さよなら
カピタン= 船長
シェフ= チーフ
ポールト= 港
ポイディオム・ヴィピエム= 飲みに行きましょう
ウォッカ= ウォッカ/アルコール
ピヴォ= ビール
バスキー= ドル |
|
 |
| ヤスミン・プラブダスは、ITFニュース・オンラインの編集者。 |
 |
英語圏の船員
船員のスラング
オーストラリア、英国、ニュージーランド、米国などの英語圏出身の船員は、船員独特のスラングを使っている。これらには、言葉のリズム(韻律)に合わせたスラングが多い。以下は、その例である。
●オールドマン= 船長
●ハリーテート= 航海士(メート)
●ジンジャー・ビア= 機関士(エンジニア)
●レッキー= 電機士
●スパーキー= 通信士
●バブリング・ブルック= 司厨手(コック)
●クラム・キャッチャー= 司厨員(スチュワード)
●スケーリーバック= AB/甲板部員
●ドンキーマン= 操機長
●ファイアメン= 機関部員(複数)
●チャネルズ= 休暇前の気分
●スターボード・リスト= 飲みすぎた船員が持つもの
●ポンプ・ザ・ビルジ= トイレに行きたい
●ゴーイング・アショア・ギア= 上陸用服装
●ピット= ベッド
●ドービー= 洗濯
●ジョブ・アンド・ノック= 仕事を早く済ませて休暇を得たとき
●ベル・ツー・ベル= 通常の労働時間
●リングボルト= 船内にいるべきでない人または物
●ドッキング・ボトル= 申告済み酒類
●ブラック・パン= 夜食(午後10時ごろ)
●カウボーイ・ヒッチ= 誤った/でたらめな結び目
海の仕事歌(シャンティー)
これらの歌は、船乗りの日々の仕事の辛さを紛らわせるために歌われていた。この種の歌には、“呼びかけと応答”形式の歌詞があり、通常は乗組員全員が参加して歌われていた。
この伝統は、英国/アイルランドおよびアフリカ/カリブ海の文化から発展したものである。これらの歌詞は、船乗りたちが異なる文化と接触することによって発生したもので、アイルランドのメロディーがアフリカやポリネシアのリズムと混じり合い、さらにアメリカの物語が溶け込んだものもある。
シャンティーは、その時に行う仕事に合わせて歌われていた。例をあげると…
ショート・ホール/ショート・ドラグ・シャンティー
手早く行う仕事、帆を絞ったり、巻き上げたりする際に歌われた。
ロング・ドラグ・シャンティー
帆の展張作業のような、時間のかかる力仕事に合わせて歌われた。各節の終りのコーラス部分で、船員は帆綱を引く手を休めることができた。
キャプスタン・シャンティー
錨の上げ下ろし作業のように、錨綱を一定のリズムで繰り出したり、巻き上げたりする仕事の際に歌われた。
フォクスル・シャンティー
仕事の終わる夕方に歌われた。一般的なテーマは、恋愛、冒険、戦いまたはユーモアであった。
ホエーリング・シャンティー
捕鯨船乗組員によって歌われた。 |
|
 |
| |