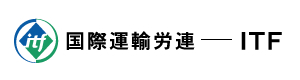|
 |
| 2009年1〜3月 第34号 |
| ■今月のニュース |
 |
| |
船員
船員の魅力を高める「Go to Sea」プロジェクト
ITFは船員という職業の魅力を高め、船員不足の解消を目指す事業に加わることを表明した。
国際海事機構(IMO)の「Go to Sea(海に出よう)」プロジェクトは、国際労働機関(ILO)、海運関連団体、ITFが賛同する全産業的な事業で、船員という職業のプラスの側面を促進し、犯罪者扱いされたり、上陸を許可されなかったりするというマイナスの側面を払拭しようとするものだ。現在、国際海運業界は経済危機に直面しているが、世界の商船隊に必要とされる、質の高い船員が不足する事態を避けるために、将来に向けて計画を立てなければならないという認識の下、訓練施設の拡充、政府への陳情、学校への広報、教宣資料の開発、女性船員の勧誘等の活動を提案している。
IMOのミトロプロス事務局長は、「現在、オフィサー(職員)は34,000人不足しており、今後の世界の商船隊の拡大を考慮し、2012年までに83,900人が不足するという最近の報告を見れば、船員不足の問題がいかに深刻なものか分かるだろう。世界の商取引の9割は海上輸送で賄われている。海上輸送は安全で、安定的で、効率的で、安価で、環境への負荷も少ない。船と船員がなくなれば、世界の半数の人々は燃料不足で凍死してしまうだろうし、もう半数の人々は食糧不足で飢え死にしてしまうだろう」と述べた。
ILOのクレオパトラ・ドンビア・ヘンリーは、これに同調して、「若者が海の仕事に魅力を感じられるよう、ILOは船員の生活・労働条件の向上に努めてきた」と述べた。 |
|
 |
東南アジア行動週間の成果
ITFが最近、東南アジアで実施したFOCキャンペーン週間の結果、地域全体で計8隻がITF協約を締結するに至った。さらに6隻についても、現在、協約締結に向けた交渉が行われている。同行動週間では、これに先立ち東アジアで行動週間を実施した際に活動の標的とされた2隻もITF承認協約に署名した。
今回の行動週間で特に目標としたのは、亡命して乗船しているビルマ人船員の条件改善であり、ビルマ人船員が乗り組んでいる8隻の船舶については、現在もITFインスペクターが監視の目を光らせている。そのうち、2隻では、二重帳簿がつけられている疑惑がある。インドネシアでは、ITFコーディネーターでもあるインドネシア船員組合(KPI)のハナフィ・ルスタンディ委員長が、水産大臣およびその顧問と会談し、人身売買や「社会的ダンピング」の問題を提起した。水産大臣は、これらの問題解決に全力を尽くすと約束した。
KPIは、また、ビルマ政府に抗議文を送付した。ITFの海事コーディネーターを務めるスティーブ・コットンは、「行動週間では、一貫して船員、港湾労働者、ITFインスペクターが、国内外で素晴らしい調整活動を行った。また、東南アジア全体の加盟組合が、組合員を支援するために協力した」と述べた。 |
|
 |
手に負えなくなってきた海賊行為
2008年は、船員の生命と生活が海賊の脅威に晒され続けた一年だった。本稿執筆中の段階で、既に200件の海賊行為が国際海運局(IMB)の海賊行為通報センター(PRC)に通報されていた。このことからも、海賊の襲撃が劇的に増加していることが伺える。ソマリア、ナイジェリア、インドネシアが依然として世界の海賊多発地帯となっている。
2008年に通報された海賊行為には、海賊による115隻への乗り込み、31隻のハイジャック、23隻に対する発砲が含まれる。計581人の乗組員が人質になり、うち、9人が殺害され、7人が現在も行方不明となっており、おそらく死亡していると思われる。
IMBのポテンガル・ムクンダン局長は、次のように述べている。「海賊が頻出し、暴力のレベルもエスカレートしていることは、海運産業と全ての船員にとって大きな懸念である。攻撃の種類、攻撃に伴う暴力、人質の数、船舶解放のために支払われる身代金の額などが、全てエスカレートしている。
海賊に襲われることにより、しばしば船員は甚大な被害を被る。人質に取られるといった目に見える被害の他、船主のコストが高くつくことから、船員の雇用条件や賃金に影響が出る可能性もある。海賊の頻出海域を避けるため、わざわざ航路を変えて遠回りする船舶も出てきた。保険料も上昇し、その一部は顧客に転嫁されることになるが、労働者のリスクも高くなる。
昨年、ITFは多くの船員の労働条件について船主と交渉し、アデン湾を航行する船舶に乗り組む船員のための追加手当の支払いと権利、船員が死亡した場合の遺族に支払われる補償金などを確保した。しかし、もっと早い段階で襲撃に備える必要がある。そのためITFは、軍隊が断固たる態度で海賊問題に対応するよう求めた。ITFは、単に防御措置を取るだけでなく、海賊母船の探索も行うよう海軍に求めている。 |
|
 |
| |
|
 |
|