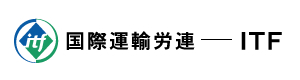| 2009年1〜3月 第34号 |
| ■エレーヌ・バーナード |
 |
| |
民主主義に息を吹き込む組合
エレーヌ・バーナードが、グローバルな組織化と力のある組合の構築を語る。
エレーヌ・バーナードは労働運動の第一人者で、労働問題の思想家、論説者としても引っ張りだこだ。ハーバード大学法科大学院の「労働と職業生活プログラム」の理事も務め、労働運動の国際比較と市民社会、民主主義、経済成長に労働組合が果たす役割について研究し、教鞭も取っている。本誌はバーナード氏に労働運動について、また、労働組合が今後直面するであろう課題について尋ねた。 |
|
 |
組合が互いに学びあう最善の方法とは?
難しい問題だ。どうやって人々に経験を共有しようと思わせるのか?そのためには、組合同士のコミュニケーションを様々な方法で促進するITFのような組織の存在が不可欠だ。
人と人とを結びつけるためにできることとして、ケーススタディーをまとめるというやり方がある。といっても、戦争の話を書くのでもないし、成功談を書く必要すらない。それを元に人々が特定の問題を検討することができ、議論のたたき台となるようなものを作成するのだ。組合員は、ケース・スタディーから明らかになった事実に基づき、組合指導者の身になって考え、指導者が行わなければならない決断について考察する。そうすることで、意思決定がどのようになされ、戦略がどのように構築されているかを知ることができる。
労働界には、あらゆる問題が特殊であり、ユニークである、と言って済ます嫌いがある。確かにそれは正しいのだが、ユニークな個々の事例からより普遍的な教訓を引き出すことが重要だし、そのためにもっと時間を割くべきだ。誰しも知りたいという欲望をもっている。まずは、異なる企業の異なる環境の中で同様の仕事をしている人々を観察してみよう。関心を同じくする人々が、どのように共同体を形成し、その結果、どのような変化がもたらされるのかを学ぶことができるはずだ。 |
|
 |
先進国と途上国は組織化で協力することが可能か?結局、先進国が方針を決定することになる危険はあるか?
途上国では、インフォーマルセクターで働く人が労働力人口の大半を占め、フォーマルセクターは非常に小さい。労働者がやろうとしているのは、インフォーマルセクターにおける雇用関係のフォーマル(正式)化だ。
一方、先進国ではフォーマルセクターにおける雇用のインフォーマル化が進んでおり、組合はこれに対処しようとしている。途上国の人々は、インフォーマルセクターの組織化の手法についても既に把握しているため、ここから教訓を得ることが可能だ。誰も知識を独占する権利はもっていない。
その他、留意しておく点としては、労働運動の形態は国によって実に様々であり、正しい組合のあり方が存在するわけではないということだ。もちろん、良い組合の要素は、いくつか存在する。民主的であること、未組織労働者を含む他の労働運動から孤立していないこと、組合に加入することができない労働者のために、組合以外の市民団体と協力関係を築いているかどうか、などである。 |
|
 |
組合は、組織化をどう進めていけばよいのか?
重要なのは、組織化について理解することだ。組織化とは、力を構築するプロセスである。目的は、あくまでも力を得ることで、組織化自体が目的ではない。究極的には、組織化とは力のないところが力を持てるようにすることである。組合員が多くても、組合員が組織され、きちんとした目的を持ち、目的のための戦略を持っていなければ、組合は力を持ち得ない。ある人が組合員であり、組合費を払っているというだけで、その人が自らを組合の力であると認識しているとは限らないからだ。
私がよくやってみるのは、組合の力がどこに所在すると組合員が認識しているかを考えてみるという手法だ。組合の専従職員が力を持っていると感じているのか?その場合、専従職員が組合の建物に足を踏み入れた瞬間に、建物の中に組合が存在することになるのか?そしてその職員が帰宅してしまったら、組合はどこへ行ってしまうのか? |
|
 |
ますます厳しくなっていく環境の中で組合はどうすれば力をつけられるのか?
環境問題の議論で、「グローバルな視点をもち、その視点をもとに地域レベルで貢献しよう」とよく言われるが、組合もこれと同じアプローチを採用してみてはどうか。
労働者のほとんどが、自分には力がないと感じている。組合は地域レベルで集まり、その地域で何がうまく行くかを話し合う必要がある。組合は問題の後始末に追われがちだが、同じくらいの時間を費やして新しい事を開始したり、組合員のやる気を起こさせたり、鼓舞したりする必要があると思う。組合は問題が発生すると何が原因かを話しあうために会合を開くが、どうすればうまく行くのか、何が正しいやり方か、良い取り組みを伸ばすにはどうすればいいかを話し合うために会合を開いてはどうか。悪しき慣行を改善し、阻止するだけでなく、組合がもっと前向きに役割を果たしてはどうか。
組織化は、すべて人がやる気を出して行動を起こすことに始まる。誰しも大切にしていることがある。労働者が何かを達成できると感じられることが重要であり、誰かと話す環境が整っていて、話すことでやる気を出すことができる機会を与えるべきだ。これこそが、まさに組織化である。
言葉にすると大げさだが、実際やるべきことは非常に単純なことである。まさに、このようなやり方で組合は結成されてきたのだ。 |
|
 |
組合がより限られた資源でより多くの時間を組織化に費やすために、他のどの活動を削減するのかは、どう決定できますか?
複雑な問題だ。基本は、常にやってきたことを、違うやり方でやることである。他の人の仕事を代わりにやることは避けるべきだ。その人間を無力化する危険があるからだ。
例えば、苦情をどう処理するか。組合の代表者が苦情処理を担当し、ペーパーワークもやって、会社とも話し合いをするのか?組織化の戦略として、組合員自らの力を自覚させるという手法を取るのであれば、まず、じっくりと話をして、同様の苦情を抱えている人間を探し出し、集団で会社に出向く。そうすれば、苦情処理も単なる事務作業ではなく、組織化の機会へと変わる。
組合のあらゆる作業を、組合員の力を構築する観点から見直してみる。次の世代の組合指導者たちの訓練と指導を支援するという観点に立った時、まずやるべきことは何だろうか?学ぶための機会はたくさんある。 |
|
 |
ロジスティックスと戦略
米チームスター労組のユナイテッド・パーセル・サービス(UPS)キャンペーンは興味深い。同キャンペーンは単にロジスティックスの分野に焦点をあてたものではなく、いかに組合員を動員し、一般市民を味方につけられるかを考えた。そしてそのために、成功事例を検討し、一般市民にも理解してもらえる理論を展開した。UPSキャンペーンの場合は、「パートタイム労働は、アメリカではうまく機能しない。パートタイム労働の問題点を認識するために、私たちはUPSのドライバーをしているわけではない」というメッセージを伝えた。これにより、一般市民もUPSのドライバーに共感することができた。こういったやり方は、実にうまくいく。問題は、会社もばかではないという点だ。組合がビジネスの要衝がどこになるかを突き止めた時には、企業は既にそのことに気付いている。
急所を見つけて、そこを掌握するために資源を投入すれば、全て組合の思い通りになるといった考えがあるが、実際はそれほど単純な話ではない。
組合の戦術とはチェスのゲームのようなものだ。自分ひとりでゲームをしているわけではない。こちらの取る行動の一つ一つに相手も反応してくる。過去にうまくいったやり方が、今後もうまくいくとも限らない。状況の変化を注視していなければならない。 |
|
 |
| |