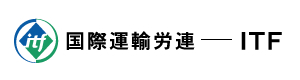|
 |
| 2009年1〜3月 第34号 |
| ■船員 |
 |
| |
船員に対する刑事訴追の環境は明らかに悪化している
最近の事例から船員の立場は日々弱くなっていることが伺える、とアンドリュー・ドレイパーは述べる。
船員に対する刑事訴追を取り巻く状況は明らかに悪化している、というのが船員組合の見解だ。船員は、しばしば訴追の標的にされやすいからだ。事件が発生し、誰かが責任を取らなければならない状況の中、船員はしばしば他から隔離された状態にあり、その国の言葉や法制度もよく理解できないまま、常に現場に居合わせることになる。
法の裁きにより、船員は不当な刑罰にさらされることになる。当局からの刑事訴追の標的になりやすく、船員の立場はますます弱くなっている。最近発生した2件の事件からもこのことが伺える。ヘベイ・スピリットのジャスプリット・チャウラ船長とシャム・チェタン一等航海士は、2007年12月に油濁の責任を問う裁判で無罪判決を受けた。この2名が職員として乗船していた石油タンカー、へベイ・スピリット号が、錨泊中にクレーンバージに激突されたのだ。
現場にいた2隻のタグボートの船長も投獄され、クレーンオペレーターも同様の裁判で罰金を課せられた。チャウラ船長とチェタン一等航海士は、韓国の司法当局が本件を控訴するという驚くべき行動に出た後も、本国への帰国を許可されていない。
一方、コーラルシー号に乗船していたクロアチア人船長は、ギリシアの沿岸警備隊が同船に積み込まれたバナナの箱からコカイン51キロを発見したために、2008年7月に14年の実刑判決と20万ユーロの罰金の支払いを命じられた。
ITFは、ギリシア法廷のラプタロ船長に対するこの判決に異議を唱えた。デビッド・コックロフト書記長は次のように述べた。「法廷に提出されたあらゆる証拠からもラプタロ船長の無実は明らかであり、このような判決は予期せぬ、有り得ないものであった。船長とコーラルシー号から発見されたコカインの間に関連があるという証拠は何もないにも関わらず、憶測と連座制の適用で14年もの禁固刑が言い渡された」ITFのスティーブ・コットン海事コーディネーターは、「今回の事件は、一人の船長の問題ではない。海上貿易の継続を身をもって担保している船員を守る能力が海運産業にあるのかどうかという問題である。この判決が覆されることがなければ、今後は世界中が依存する迅速かつ効率的な海上輸送サービスは存在しなくなるだろう。積載された果物のパレットやコンテナを逐一チェックすることが、全ての船舶の船長に求められるようになるからだ」と述べた。 |
|
 |
船員の公正な処遇
「海難の際の船員の公正な処遇」に関するガイドラインの存在は、船員の人権を擁護する宣言文であると広く認識されている。同ガイドラインは国際海事機関(IMO)と国際労働機関(ILO)の合同作業部会で策定され、その際にはITFも意見を述べた。どこで発生した事故であろうとも、海難の際には船員の権利が擁護されることを担保するためのガイドラインのはずである。
IMOによると、「海難に伴う船員の不公正処遇」に関する情報提供を求めるIMOの回状2825号に回答した加盟国は、9月末の時点で次の13カ国であった:バハマ、ブルガリア、エストニア、フィンランド、ドイツ、ホンジュラス、モーリシャス、メキシコ、モロッコ、パナマ、カタール、サモア、スペイン。これら13カ国は全て、船員が不公正な処遇を受けたとの報告はない、と回答した。
ITFは、刑事訴追から船員を守ろう、と声高に主張してきた。2008年7月、ITFと国際船主協会の円卓会議メンバーは、ヘベイ・スピリット号の職員2名に無罪放免の判決が出たにも関わらず、韓国の司法当局が拘留し続けたとの報告を受け、驚愕と落胆と多大なる懸念を表明した。2名の拘留は、今後の審問の状況次第で、長ければ1年に及ぶ可能性もある。「このような処遇は不公正かつ非合理であり、人権侵害にあたる。2名の本国送還を強く求める」と、円卓会議のメンバーは声明文の中で述べた。
国際海運の使用者団体、バルチック国際海運協議会(BIMCO)は、船員に対する不公正な処遇の問題を数カ国の政府に提起した。韓国政府に対しては、ヘベイ・スピリット号の件で掛け合った。BIMCOは、加盟国にも同様の行動をとるよう促している。
BIMCOのミカエル・ルンド国際問題担当部長は、船員が不当な処遇を受けた場合はすぐにIMOとILOに報告して欲しいと加盟国に促したが、果たしてそのような事例があったとしても、加盟国が報告するかどうかは疑わしいと述べている。
最近、ドイツのハンブルクで国際海洋法裁判所(Itlos)が主催したセミナーで、船員が外国で拘留され、拘留国が非協力的な場合においては、裁判所を活用し、問題解決を促進する方策を探った。
このセミナーで、裁判所が船員以外の保釈を許可していると思われることは受け入れられないことを確認した。船員の場合は、保釈金の支払いや他の保障も適用されなかった。
国際海洋法裁判所(Itlos)は中立かつ独立した恒久的組織であり、国連海洋法条約(UNCLOS)の解釈や適用をめぐって発生する争議を裁くことを目的としている。海洋法に精通しているとの評判の高い21人の独立した判事から構成されている。
判事は国連加盟国から選出され、任期は最低でも9年である。3年ごとに判事の3分の1が改選される。同じ国から複数の判事を送ることはできず、同裁判所は、地理的に偏りなく各国から輩出された判事から成り、世界の主要な司法制度としての役割を果たしている。 |
|
 |
刑事訴追と上陸
ノルウェー職員組合(NSF)の海事部長で、国際船長協会の副会長も務めるビョーン・ハーブも、船員にとっては状況がどんどん不利になってきている、とITFと同じ懸念を持っている。ハーブは、全ての根源はISPS(船舶と港湾施設の国際保安)コードにある、と見ている。本誌の取材に応じてくれた多くの人々と同様、ハーブも特に船員の苦労を増やしている国として米国を挙げた。
「ノルウェー人の船員でも、適切なビザを持っていなければ、米国への上陸は許可されないだろう。しかし、観光客として米国に行く場合、ビザは必要ない。船員がこれをどう感じるか、想像に難くない」とハーブは言う。
「NSFはこの問題をIMOとノルウェー政府に提起したが、政府からは返事すら来ない。エジプトでも同様の問題が発生した。3−4ヵ月前、エジプトが突然、全ての船員の上陸を拒否したのだ。この事実を知った後、エジプトのIMO代表にこのことを話した結果、数時間で問題が解決した」
ハーブは、船員に対する刑事訴追の問題に何年も取り組んできたが、最近状況が悪化しているのは何故なのか分からないと言う。「大抵の場合、各国の政府がスケープゴートを探していることが原因のように感じる。事故の責任を問える相手が見つからない場合に、船員を責めるというわけだ」とハーブ。
ハーブは、ほとんどのケースにISPCコードと米国が絡んでいる、と言う。「NSFは職員を対象に調査を実施したばかりだ。合計1,600通のEメールを発信したが、回答率は3割だった。回答者の多くが自分の受けた処遇を不満に感じていた。全員ではないが、米国に対する不満を多くの船員が表明した。回答者の5分の1が、過去2年間に米国で上陸を拒否されたことがある、と回答した。
「こんなこともあった。ノルウェー人の船長が航海の後、米国で下船して休暇を取った。休暇中にパナマにも行って、旅行者としてノルウェーに帰国したが、何も問題は起きなかった」とハーブは述べる。
ハーブの話では、2005年にもNSFは同様の調査を実施したが、当時も結果は全く同じだったという。「船員の将来は、全く明るいものではない。ITFやこの問題に関してITFと協力する意思のある使用者団体と同様、ハーブもまた、こうした現状は船員のリクルート面にも悪影響を及ぼす、と確信している。また、コットン海事コーディネーターは、「この問題がもたらす悪影響を軽視するべきではない。無実の船員を守るため、もっと行動する必要がある。海運産業がこの状況を管理できないのなら、現在、既に顕在化している船員不足の問題は、『船員飢饉』問題へと発展するであろう」と述べた。 |
|
 |
最近の2つの事件
ヘベイ・スピリット号事件
誰が?:ジャスプリット・チャウラ船長とシャム・チェタン一等航海士
いつ?:2007年12月7日
どこで?:韓国の大山(テサン)港
何が起きたのか?:
原油を満載した26万dwtの超大型原油タンカー、ヘベイ・スピリット号は、錨泊中に通過中のクレーンバージに激突されたが、原油の流出に関しては無罪、との判決が出た。船倉に穴が空き、原油が海上に流出した。検察側は控訴し、2人は帰国を禁止された。現在、2名の職員は、帰国が許可されるのかどうか、控訴審の判決を待っている。
コーラルシー号事件
誰が?:クリスト・ラプタロ船長と2人の乗組員
いつ?:2007年7月
どこで?:ギリシア
何が起きたのか?:
クロアチア人のラプタロ船長は、14年の実刑判決と罰金20万ユーロの支払いを命じられた。ギリシアの沿岸警備隊が同船に積載されたバナナの箱から51キロのコカインを発見したためだ。裁判の手続きがギリシアの法曹界でも大きな懸念の対象となっている。3名は、本件への関与を全面的に否定し、また、有罪を示す証拠がないにも関わらず、たびたび保釈を拒否された。2008年11月27日、ラプタロ船長の無罪が証明され、17ヶ月に及ぶ試練が終了した。ITFのスティーブ・コットン海事コーディネーターは次のように述べた。「事件が発生した際、世論に迎合し、通常外国人である船舶の職員を非難するという手っ取り早い手段に訴えることは慎むべきだ、ということを当局は学ぶ必要がある」
|
|
 |
| |
|
 |
|