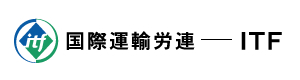|
 |
| 2009年1〜3月 第34号 |
| ■公共交通 |
 |
| |
地域の公共交通は自治体の所有で
ITFは昔から公共交通の促進を強く訴えてきた。ITF都市交通委員会が策定中の公共交通憲章が依然として民営化反対を掲げている理由をマーチン・メイヤーが説明する。
ITF都市交通委員会は1980年代半ばから、「公共交通の所有と管理」という極めて政治的な問題に取り組んできた。1986年、英国で地方バスの規制緩和・民営化が実施されて以来、公共交通の規制緩和・民営化が急速に政治的なトレンドとなり、欧州諸国を初めとする各国政府がこれを追求し始めたからだ。支出削減や減税の方法を模索していた諸政府は、自治体の資産売却で得られる、この一度限りの多額の収入に心を奪われ、民営化による効率アップ、革新、補助金削減を説く右派エコノミストに傾倒していった。
ITF加盟組合の中には、初めのうちは、民営化には必ずしも反対ではないものもいた。例えば東欧では、国家組織があまりにも官僚的で、労働者のニーズが無視されていたため、組合の中には、民間セクターの方が必要なインフラ投資が行われ、長年の非効率も解消され、ひいては、賃金・労働条件の改善につながるのではないか、と期待したものもいた。
しかし、民間業者が求める改革を実際に経験すると、ほとんどの組合が考えを改めた。公共交通の民営化で典型的に行われるのは、人員整理、労働時間の延長、新規採用者の給与水準の切り下げ、有給休暇・病気休暇・年金等の各種労働条件の切り崩しだ。民間業者が、人件費(通常、コスト全体の50%を優に超える)を抑えることで、利潤の最大化を追求しようとするのは自然なことだ。 |
|
 |
公共交通憲章
ITF都市交通委員会は現在、「ITF公共交通憲章」を策定中で、その最終段階にある。この憲章には、地域の公共交通の規制緩和・民営化に反対する声明も含まれている。この声明は、民営化を受け入れざるを得ない立場に立たされている加盟組合をも支援すると同時に、規制緩和型の民営化よりも、労働者の賃金・労働条件を最大限に保障する、厳しく管理された民営化を追及するよう促している。また、賃金・労働条件に対する攻撃から組合員を守るためには、強い労働組合の存在が欠かせないことを明確にするとともに、公共交通の管理・財源については、民主的な選挙で選ばれた地方議会に強い役割を持たせ、地域のバス、路面電車、地下鉄は自治体に所有させるというモデルを提唱している。
また、自家用車の真の代替手段としての公共交通を整備・促進するために、公共交通への投資増大を提唱している。公共交通は清潔で近代的で便利で信頼性が高く、時刻表や料金は簡潔かつ分かりやすいものでなければならない。真のモーダルシフトを実現し、労働者とその家族の負担を減らすためにも、料金補助を積極的に奨励する必要がある。また、高齢者、身体障害者、乳幼児連れの人にも利用しやすいサービスが求められている。
ITF公共交通憲章は、安全と治安、特に暴力的・非社会的行為についても取り扱っている。労働者や乗客を暴力から守るためには、特別な対策が必要だ。また、渋滞や大気汚染の解消には、公共交通ネットワークの整備が不可欠であり、これにより、化石燃料の依存度を減らし、気候変動をやわらげることもできるだろう。民営化による市場の気まぐれにまかせておくだけでは、必要とされる投資やサービスは実現しない。政府が積極的な政策を打ち出し、財源を確保することが重要だ。 |
|
 |
賛同する組合
最近のITF路面運輸総会で、原油高に関する決議が採択され、自家用車への代替手段として公共交通を促進することの重要性が再認識された。労働者は特に原油高の影響を受けやすいが、代替手段としての公共交通が整っていない場合には、高騰するガソリン代を払い続けるしかない。この決議は、各国政府に対して、交通運輸や気候変動に関する政策を見直し、公共交通への投資を増やすよう、圧力をかけることを加盟組合に要請すると共に、市場にまかせておくだけでは必要な変革をもたらすことはできない、と警告を発している。
ITFは加盟組織の運動を実務的に支援することを約束している。実際、民営化という国策に抵抗する加盟組合を支援してきた歴史を持ち、成功を収めた例もある。規制緩和・民営化を既に経験した組合を未経験の組合に紹介するなど、加盟組合が相互に連絡を取る手助けもしている。英国の運輸一般労組(TGWU ※現在はユナイトの一部)は、ITFを通じて他の加盟組合の大会に出席し、民営化や規制緩和がもたらす悪影響を警告する演説を行い、民営化が恩恵をもたらすと主張する事業者や政府の情報が誤ったものであり、神話に過ぎないと訴えた。
民営化の方向を実際に転換させた例は少ないが、その意義は大きく、ITF加盟組合による運動の直接の成果だと言える。英国では、鉄道労組が長年にわたり、鉄道民営化に反対の声を上げてきた。鉄道民営化は、結局、納税者への負担が大きく、安全性は驚くほど低下し、特に保線要員の雇用・労働条件に深刻な影響が及んだため、労働党政権は線路・インフラの所有・管理会社である「レール・トラック」の再国有化に踏み切った。しかし、運行は依然として民間業者が行っている。
ニュージーランドは、民営化が高コストで納得のいく成果が出なかったため、労働党政権が全ネットワークを買い戻した。その他の国でも、民営化が期待された成果をもたらさないことが明らかになり、民営化推進の声は縮小している。しかし、ドイツでは依然として、鉄道の民営化を推し進めている。最大鉄道労組のトランスネットが一定の支持をしていることも背景にある。
一方、地方バスの規制緩和・民営化の発祥地、イギリスでは、最大バス労組のTGWUが長年、運動を続けた後、前向きの変化が現れ始めている。現在、国会で審議中の法案が可決されれば、地方自治体が再びバス事業をコントロールする道が開かれる。入札により、バス事業を民間業者に委託する権限が与えられるのだ。これにより、少なくとも、民間業者が自由にサービスを切り下げ、料金を引き上げ、多額の利益を手に入れることを許してきた、これまでの規制緩和を改めることができるだろう。
ITFに加盟する労働組合は、新自由主義という政治課題に、これまで以上に関心を抱いている。民営化、特に規制緩和と一体となった民営化モデルは見事に失敗し、期待された成果を生み出すことができず、国および地方自治体にとってもコストのかかる事業だったことが益々、明らかになっている。
各国政府は燃料高騰や気候変動の問題を考慮に入れて、交通運輸政策を見直さなければならない。公共交通部門を組織する労働組合は、今後ますます、公共投資の拡大、バス・鉄道サービスの積極的拡充政策、民営化・規制緩和の見直しを要求する上で、主導的な役割を果たすことになるだろう。
|
|
 |
| ユナイト(英国)TGWU部門のマーチン・メーヤーはITF路面運輸部会の議長。 |
 |
| |
|
 |
|