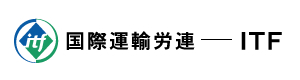|
 |
| 2009年7〜9月 第36号 |
| ■オピニオン |
 |
| |
オピニオン
イスラム教は民主主義や労働者の権利と矛盾しないとハナフィ・ルスタンディは述べる。
インドネシアでは、最近、10年間で民主制移行後3回目となる総選挙が行われた。今回の選挙は、インドネシアの歴史上、そして世界的に見ても、最大かつ最も平和裏に実施された選挙の一つだ。中央議会、地方議会の約1万5千人の議員を選出するため、1億7千万人を上回る有権者が全国50万ヶ所に設けられた投票所へ出向き、選挙は成功した。今回の選挙も完璧とはいえないが、暴力沙汰や強制行為、脅し行為などは見られなかった。
世界最大のイスラム教国家、インドネシアは、世界第3の民主主義国家として道を切り開き、主としてイスラム教に根付く理想と、あらゆる宗教や多種多様な民族への健全なる尊重をユニークに融合させるモデルを生み出した。インドネシアはこの10年間の進歩を誇りに思い、明るい未来を目指していくべきだ。
イスラム教の教えは、西欧諸国の定義するいわゆる「民主主義」を許容しないため、イスラム教と民主主義は相容れないと言う者もいるが、最近の事例から、そのような学識者の主張は間違っていることが証明された。インドネシア人は、イスラム教の理想が、公正かつ自由に選挙で選ばれた政治家によって支えられる強い国家と完全に両立できると考え、大きな誇りをもって前進してきた。もちろん、インドネシアにもしばしば汚職は存在するし、進歩を妨げる無能な政治家はいる。トルコの仲間と同様、インドネシアも、自信をもって前進していくため、イスラム教の文化や信仰と、選挙を通じた人民のための人民による政府とを融合させ、確固たる中道の立場を見出してきた。
一方、イスラム教の教えと美徳を崇め、人々の自由を求める声を無視し、結果として国民が不利益を受けている国もある。そのような国の一つであるイランは、中東を支配したいという熱意と欲望のため、発展が遅れ、世界中へ憎しみを広げている。1979年のイスラム革命によってもたらされた大きな進歩をさらに前へ進めるどころか、一般のイラン人の信条からはかけ離れた政策を採用していることが主な原因となり、イランの成長は妨げられている。イランは、宗教や人種の面でも真のるつぼと言える。シーア派、スンニ派、クルド人、バハイ教徒、バルーチ族、アゼリー人などは多数の中のほんの一例に過ぎない。
また、地球上でも最も若者の多い国でもある。一見、これは強みに思われるが、イラン政府は現行の強硬路線を維持するため、このような多様性を絶えず抑圧してきた。
我々は、イランの人々が真に直面している問題についてよく調べることなく、イラン人に「強硬派」のレッテルを貼りがちだ。その多くが、大規模で非常に不安定な警察国家や、思考の自由、言論の自由、自由かつ公正な選挙を妨げる悪意に満ちたプロパガンダによって増長されている。一般の市民が自由に思想を表現することは許されない。インターネットすら自由に使うことができないため、時代錯誤が甚だしい。一方では、インドネシアのように、未来を見据えて前進しているイスラム国家もある。
現在、イラン政府の政策は、表向きは全体主義で、本質的に暴力に満ち、文化、宗教、思考の多様性を抑圧し、支配力を維持するためには何をも辞さない。
現在のイランの政治の最大の犠牲者はイランの国民、すなわち、青年、学生、女性、労働者であり、まさに国家存続のための活力源となる人々だ。対照的に、インドネシアでは、勤勉という強い文化に支えられ、政府は組織労働者を支援している。イランの労働者は労働条件を交渉する権利も、自らの処遇について疑問を抱く権利も持てない。声を上げるために労働者が起こした最も基本的な運動すら、暴力的に抑圧される。政府の見解に反する意見を表明した労働者、学生、女性などが、しばしば拘留され、投獄され、拷問され、殺害されることすらある。
本稿執筆中の現在、イランでは大統領選挙の準備が進んでいる。イランの群集がこぞって投票に出向き、今日のイランの元凶となっているハメネイ師の政策にはっきりと異議を唱えてくれることを願う。インドネシアはイランと同様、イスラム教国家だが、民主主義とイスラム教の共生が可能であることを示してきた国民として、インドネシア人はイランの人々に連帯し続け、最善の未来がもたらされるように祈り続けるべきだ。 |
|
 |
| ハナフィ・ルスタンディは、インドネシア船員組合(KPI)委員長兼インドネシアITF加盟組合協議会議長。 |
 |
| |
|
 |
|