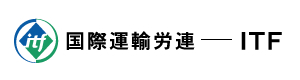|
 |
| 2009年7〜9月 第36号 |
| ■HIV/エイズ |
 |
| |
ケニアの港湾労働者、エイズ政策を勝ち取る
ケニアの港湾労組は、職場のHIV/エイズ政策の策定を求めた港湾当局へのロビイングに成功した。今年初め、6000人の労働者を雇用するケニア港湾局が、モンバサ港で前向きな政策を策定した。この政策の策定にあたり、ITFに加盟するケニア港湾労組が主要な役割を果たしたが、同労組は政策の実施状況のモニタリングにも関与することになろう。 |
|
 |
政策が労働者にもたらす恩恵は?
ケニア港湾労組のサイモン・サング書記長によると、この政策によって、労働者が職場でエイズに対する偏見や差別に対処しやすくなるという。また、職場で行われるHIV/エイズ関連の活動を支援したり、継続したりする上で、資金が確保できるようになる。同政策は労働者だけでなく、扶養家族も対象としており、組合員の家族全員に抗レトロウィルス薬を支給することを規定している。
同政策の中心となる原則は、HIV感染している、あるいは感染の疑いがあることを理由に、従業員や従業員の扶養家族、求人への応募者などを、雇用、訓練、昇進、従業員手当、サービスなどの面で差別してはならないというものだ。 |
|
 |
ケニアではHIV/エイズの問題はどれほど深刻か?
最近のケニア・エイズ指標調査から得られたデータでは、ケニアの感染率は7.4%となっているが、感染者の大多数が、自らが感染していることを認識していない。そのため、適切なケアや治療を受けることもできない。また、どうすれば、セクシャルパートナーや子供たちをHIV感染から守ることができるかを学ぶ機会も得られない。ケニアの患者・感染者140万人のうち、83%にあたる約100万人は、自らが感染しているという自覚がない。
男性よりも女性の感染リスクが高く、HIV/エイズが原因で女性の方が寿命も短い。国が設定した予防・ケア・治療の目標を達成するため、ケニア政府は2010年までに国民のHIV検査受診率を8割まで引き上げるための集中プログラムを開始した。この目標を達成するため、医療機関では、検査やカウンセリング活動が加速している。また、移動型の自発的カウンセリング・検査(VCT)設備、一軒一軒を回る個別訪問、アウトリーチ(啓発・教育)活動なども活発化している。これらの運動により、現行のHIV検査サービスが補完されることになろう。 |
|
 |
その他に組合がしてきたことは?
毎年職場で行われる部署対抗サッカートーナメントの際にVCTプログラムを宣伝したりするなど、HIV/エイズ意識向上プログラムを計画した。組合のピア・エデュケーター(仲間を教育する教育者)がこうしたイベントに参加し、HIV/エイズに関する劇を上演したり、詩を暗唱したりした。こうしたHIV/エイズ関連の活動は、サッカーの試合のハーフタイムに行った。そうすることで、ハーフタイムの間もサッカーファンを退屈させることなく、かつ情報提供もできるからだ。ピア・エデュケーターたちは、サッカーの比喩を用いて、「『裸足』のプレーは止めましょう。地面はトゲだらけで危険ですから」と警告し、安全なセックスを奨励した。
女性のサッカーチームもまた、トーナメントの最終日に模範試合を行った。試合には所属部署の応援のため、たくさんの従業員や使用者が駆けつけ、大いに沸いた。
昨年、ケニア港湾労組は、ケニア港湾局と協力し、ラムで男女平等とHIV/エイズに関するワークショップを主催した。ラムは人口約10万の小さな島で、住民の大部分がイスラム教徒だ。組合がこの地域でワークショップを行ったのは初めてだったため、組合員も会社も熱が入った。ワークショップでは、性行動や、HIV/エイズの感染につながる要因、予防のための女性の能力開発の重要性、偏見や差別への対処など、職場におけるHIV/エイズ対応が話し合われた。
ITFに加盟するケニア鉄道合同労組などの労働組合が、国にHIV/エイズ対策を取らせる上で大きな役割を果たした。組合は、まずピア・エデュケーション(仲間同士の教育)活動を全ての労働者に広げ、職場におけるHIV/エイズ・プログラムを開始した。ピア・エデュケーターは、労働者が正しい知識を身につけ、HIV/エイズに関する作り話や誤った認識を正していく上で活躍した。また、労働者がVCTやコンドーム、性感染症の管理などにアクセスできるように支援した。最近、組合は特別なVCTセッションを行い、多数の組合役員や組合員が参加した。こうしたセッションを行うことは、国民のほとんどが自分の感染状況を知らないという環境では極めて重要だ。 |
|
 |
| |
|
 |
|