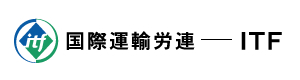|
 |
| 2009年7〜9月 第36号 |
| ■成功への道 |
 |
| |
成功への道
南アフリカの路面運輸労組は団体交渉を通じて、不安定な雇用形態の改善を求めて闘っている。
「R」は、ITRリクルートメント社(以下、ITR)によって、2000年にはトラックの乗務員として、2007年には運転手として採用された。現在は「常用」とされている。契約社員とは違い、フルタイムで働いているが、製粉・とうもろこし工場の製品輸送という彼の仕事に何ら常用性はない。ITRが「R」の住む町で契約をとっているのはこの工場だけなので、ITRの従業員の生活はこの工場にかかっている。
この工場は、種々の食品製造工場を所有する大手グループ、SAKOのものだ。かつては、SAKOの工場には輸送部門があり、全製品の輸送を担当していた。しかし、1990年代にオーナードライバー制度が導入され、運転手の従業員はトラックのオーナーに転換させられ、賃金の代わりに、輸送貨物(トン)ごとに料金が支払われるようになった。
2000年、政府が労働法の改正を提案した時、改正点の一つに、誰を従業員と見なすかに関する前提が含まれており、オーナー・ドライバーは従業員と見なされることになっていた。そうなると、オーナー・ドライバーには他の従業員と同様に労働法が適用されることになり、それを望まなかったSAKOは、工場の製品輸送をスーパー・グループという業者に下請けに出した。
工場が直接、ITRと契約するのではなく、まず、スーパー・グループに下請けに出し、そのスーパー・グループがITRと契約する。人材派遣業者のITRは、「R」のような労働者をスーパー・グループに提供し、スーパー・グループがそれをSAKOに提供する。人材派遣業は、南アフリカの労働関係法(LRA)では、「一時雇用斡旋業」と位置付けられているが、これは、「R」の例を見れば分かるように、誤解を招く言葉だ。LRAには、一時雇用の定義付けがなされていないからだ。つまり、「R」は無期限に一時雇用され得るわけだ。実際、「R」の同僚の中には、3年以上もこのような形態で雇用されている者がいる。 |
|
 |
人材派遣業のウソ
派遣労働の利用は、労働力をアウトソースすることでコスト削減を狙う企業戦略の一部だ。企業は人材派遣というまやかしを隠れ蓑にして、この戦略を正当化している。「中核業務」に専念する必要性を強調するが、そもそも何が中核で、何が非中核かは不明瞭だ。小麦やとうもろこしの製品輸送は、明らかに工場の中核業務だ。全てのアウトソーシングに言えることだが、その目的は労働コスト、特に単純労働コストの削減だ。オーナー・ドライバーは、乗務員を雇う費用も負担しなければならない。仕事がないときには、オーナー・ドライバーにも乗務員にも報酬はない。
オーナー・ドライバー制度は、雇用関係のリストラの最たる例で、運転手の地位は従業員から個人事業者に変更させられる。管理職、現場監督、職場代表までもが、人材派遣会社から供給されている例もある。
このような現象は、職場を越えて、労働階級をも分断する。アウトソーシングという戦略や、それを正当化する言葉の使い方も、企業が作り上げた制度の一部だ。今日、リストラが避けられないと思われる状況の中で、中小企業やサービス産業(オーナー・ドライバーや人材派遣業など)で雇用が生み出されているという主張は、リストラの影響を少なく見せるためのものに過ぎない。公式の統計がこのような主張を裏づけてはいるものの、実際には、生み出された雇用は新規の雇用ではない。
労働組合は、伝統的な職場の消滅に対応していく必要がある。そのためには、自分たちの統計を使って、自分たちの言葉で、自分たちの制度を作り上げていかなければならない。その目的は、企業が実施したリストラの責任を企業にとらせることにある。サービス業者や仲介業者に雇用される労働者は“非中核”として位置づけられがちだが、それは間違いだ。“中核”企業とサービス・仲介業者の契約によって、これらの労働者は都合よく管理されているだけだ。 |
|
 |
団体協約で問題を解決できるか?
南アフリカの労働関係法が、故意にあるいは無意識に人材斡旋を奨励しているのなら、法改正をすることが適切な対応策に思われる。実際、1995年以来、経済開発労働委員会(NEDLAC)に改正案が提出されてきたが、実現には至っていない。現在は選挙が近付いているため、労働相は人材斡旋業を人身売買につながるもので、違憲であるとし、禁止を訴えている。
しかし、人材斡旋を合法とする法律が、憲法制定以前に採択されている状況において、その違法性を主張するのは難しい。いずれにしても、禁止に反対する勢力が存在するのは明らかで、この問題が決着するには、何年もかかるだろう。だとしたら、それまでの間に何をすればよいだろうか?また、禁止が実現した場合、企業が他の手段を使ってこれまでと同じ成果を上げようとするのを防ぐにはどうしたらよいだろうか?
「R」の例が示すように、人材派遣業が禁止されれば、ITRはスーパー・グループとの契約を失う。もしくは、自らを運輸業者と定義し直す必要が出てくるだろう。どちらにしても、スーパー・グループと工場の関係に影響が出るわけではないし、工場と他のサービス業者(清掃請負業者等)との関係が変わるわけでもない。
規制は一般的に国家の機能として認識されている。人材派遣の禁止は、最も抜本的な上からの規制と言えるだろう。しかし、規制は下から行うこともできる。与えられた情況の中で対応すべく国家等に圧力をかけたり、団体交渉を通じて企業に要求したりすることもできる。「R」の組合が取った方法は、下からの規制の一形態を示しており、長期的には、人材派遣を含む現状への対応策として、より効果的に機能する可能性を秘めている。
まず、「R」の組合がしたことは、派遣業者に雇用されている労働者の組織化だ。これらの労働者の地位は不安定で、組織化に伴う障害は数多く存在する。一方、彼らの組織化を通じて、組合は、人材派遣が生み出す問題を、彼らと“中核的”労働者との分断を広げることなしに、彼らと共に解決していく必要性を実感している。
第二に、団体交渉を通じて、人材派遣をより効果的に規制しようと試みている。最も重要な要求は、派遣労働者の最低賃金を他の労働者に適用されている最低賃金と同一にすることだ。業界の全ての企業と協約を締結することで、これが実現できる。さらに、派遣労働自体の制限も団体交渉を通じて実現させた。
まず、12ヵ月を超えて従業員の30%以上を派遣労働者で充当してはならないことを団体交渉を通じて約束させた。さらに、労働法には一時雇用の期限が設けられていないが、「R」の組合の労働協約は「2ヶ月を超えて継続的に1社以上に派遣される労働者は、通常の従業員とみなされる」と規定し、労働者が派遣業者に無期限に雇用されるのを防ごうとしている。
この協約に問題が全くないわけではないが、団体交渉を通じて派遣労働を規制しようとする、最も意欲的な取り組みの一つといえる。雇用のアウトソーシングを含む、企業の行動は、企業に責任を取ってもらうことによってのみ、これらのプロセスを抑制することができる。 |
|
 |
人材斡旋業の歴史
人材斡旋業は常に合法と見なされていたわけではない。国際的には、長い間、労働を有償で調達・提供することは違法とされていた。「労働は商品ではない」というのが当時のスローガンだった。
第二次世界大戦後、米国のマンパワーや欧州のアデコなどが人材斡旋の合法性を主張し、一連の裁判を起こした。その結果、人材斡旋業者(代理店)を斡旋される労働者の使用者とみなす国が現れ始めた。
合法化に向けて大きく風向きが変わったのは、1997年に採択された民間職業紹介所に関する条約だ。ここで言う民間職業紹介所の概念は、人材斡旋会社よりも広いものだが、ここで初めて「業務を割り当てかつその業務の遂行状況を監督する自然人又は法人である第三者に割り当てる目的で、労働者を雇用することからなるサービス」を提供する代理人が認められた。そしてこれが、人材斡旋業の合法性を認めたものとして、認識されるに至った。 |
|
 |
| |
|
 |
|